「私たちにとってお茶の時間とは、立ち止まり、精神を落ち着かせて自分と対話するためのものです」
そう語るのは、台湾茶の香水ブランド「P. Seven」を創業した茶道師出身のパフューマー・潘雨晴(Pan)さん。2022年、ブランド10年目の節目に7年ぶりとなる新しい茶香水シリーズ「奉茶(フォンチャー)」を発表した。
そのうちのひとつ「Aged Tea 暗香」は、香水界の権威である嗅覚アートのコンペティション「アート・アンド・オルファクション・アワード2022」のインディペンデント部門でグランプリを受賞するなど、世界中に“台湾茶香水”の名を広めている。

自社ブランド「P. Seven」のほか、台湾の各都市、桃園国際空港オリジナルの香り「国門香」をはじめ、スターラックス航空など、数々のブランドオリジナルの香りを開発するPanさんに、自身にとっての台湾茶や、あらゆる香りをデザインする調香哲学を語ってもらった。
茶道師が、台湾茶の香水のパフューマーになるまで

「毎日欠かさずお茶を飲むので、忙しくて飲めない日々が続くと、自分に対して申し訳なく思う」
ちょうど1年ほど前に取材で会ったPanさんは、多忙のあまり毎日のルーティンである台湾茶を楽しむ時間すら取れていないと話していたが、最近では毎日2回程度はお茶を楽しむ時間を取り戻したそうだ。
Panさんは、台湾「圓山ホテル」のサロンで5年間ほど茶道師を務めたのち、「台湾茶の香りを香水として表現したい」と、2012年に台湾茶香水ブランド「P.Seven」を創業。
「世界に紅茶や緑茶の香水はあるけれど、台湾茶の“香りの層が変化していく”という魅力を伝えたい」と台湾茶文化を体現することにこだわり続けてきた。

「P.Seven」の台湾茶香水はたちまち話題となり、日本にも出店。着実にファンの心を掴んできた。
シグネチャー的な存在なのが、ミルクのような香りと味わいのある「金萱(キンセン)茶」という台湾茶を表現した香り「茗」。それ以降も馬告、檳榔、米酒、生薬といった台湾特有の素材を用いたフレグランスを手がけ、人気を博してきた。
だが、意外にも「金萱茶」以外に、長らく「台湾茶香水」は出されていなかった。
そして2022年、7年ぶりとなる新しい茶香水として発表されたのが「奉茶」シリーズ。「奉茶」とは、通りすがりの人にお茶をふるまうという、台湾の伝統的な習慣だ。
「昔ながらの『奉茶』とは少し違いますが、今でも台湾人は家やオフィスに来客があると、お茶をふるまいます。現代のライフスタイルに合わせながら、この文化が日常に定着しています。お客さんにお茶を淹れるような気持ちで作ったのが、この奉茶シリーズです」

「お茶の香水」は花の香り? 欧米とアジアの違い
そもそも、なぜPanさんは7年間も台湾茶の香水を作らなかったのだろう。
「実のところ、台湾茶の香りというのは表現するのがとても難しいからなんです」
「お茶にとって、香りとはとても重要なものです。白茶や緑茶、紅茶など、世界にはさまざまなお茶の香水がありますが、香水の世界では“花のような香り”というものが多いんです。この傾向は特にヨーロッパやアメリカに強いと思います」
Panさんによれば、ヨーロッパやアメリカと、台湾のお茶の文化は大きな差があるという。
「西洋では、お茶というのは友人や家族と一緒に過ごす時間、おしゃべりをしながら楽しむものですが、私たちにとってお茶の時間とは、立ち止まり、精神を落ち着かせて自分と対話するためのものです」
「日本も同じではないですか?」とPanさんは問いかける。

「もっとも、日本は茶葉本来の“新鮮さ”を重視するのに対し、台湾は焙煎や発酵といった“茶葉を摘んだ後の工程における技”に重きを置くという違いがあるように思いますが、だからこそ、私たちと西洋の人々にとって“お茶の香り”に対する解釈は感じ方が違うのだと思います」
この「奉茶」シリーズの3種類の香りでは、そうした台湾茶のオリエンタルな魅力を「パーフェクトに表現できた」と話すPanさん。
シリーズの中でも、Panさんが昔から愛飲している2、30年発酵・熟成させられた「老茶(らおちゃ)」を表現した「Aged Tea 暗香」は、香水界の世界的権威である嗅覚アートのコンペティション「アート・アンド・オルファクション・アワード(A+OA)2022」のインディペンデント部門でグランプリを受賞した。

台湾茶の中でも、年月をかけて奥深い味わいが生まれる「老茶」の香りで、グランプリを獲得──。Panさんは、この快挙をどう捉えているのだろうか。
「ありがたかったのは、このコンペティションでは、どのブランドの香りかが明かされないまま審査が行われることです」
「スイスやイタリア、フランスのような香水の歴史が深い国々のブランドと競い、私たちが結果を残すことができたのは、“彼らがこのような香りを体験したことがなかったから”ではないでしょうか。『この香りはなんだろう?』と思ってもらえたのだと思います。審査団のコメントを見ても、だいたいそのような内容でした。オリエンタルな香りを感じてもらえたということです」
ウイスキーやバラの香りをどう表現する? 調香の仕事

「Oolong Tea 沁香」では、早朝、茶摘みの時間帯ならではの、茶園の清々しい空気感を。
「Aged Tea 暗香」では、数十年以上寝かせた老茶の豊かさを。
「Formosa Beau-Tea 玉香」では、東方美人茶の、焙煎した感じと紅茶のような艶やかな味わいを──。
「奉茶」シリーズでは、台湾茶のオリエンタルな世界観を的確に香りへと昇華させているが、Panさんはパフューマーとして香りをどのようにデザインしているのか。その哲学についても聞いた。
「香りのデザインは、絵を描くことに似ていると思います」

「先ほど、お茶の香りは表現しにくいと言いました。お茶の原料から採ることのできるアブソリュート (Abusolute、植物性の原材料から溶剤を使用して抽出された香気成分)は非常に少なく、採取してもすぐになくなってしまうんです。では、それをどうやって残すか? 私はいつも、他のアイテムの香りを合わせることで、それらを表現しています」

「たとえば、私は以前ウイスキーブランドのために香水を作ったことがあります。ウイスキーのスモーキーな香りを出すために、『ピート』と呼ばれる泥炭が使われていて、私はそれを表現するために、『丁香(ちょうこう)』という生薬を使いました」
「皆が一般的にいう『バラの香り』も、私にはわずかにハチミツの香りがするように思えます。だからバラの香りを表現するために、私はハチミツの甘い香りを用いています」

Panさんは、「この仕事には、感受性と、連想力が不可欠」と語る。そして、「原料を的確に使いこなす力も必要」とその専門性を表現する。
実際に、香りをデザインするときには、絵を描いて、イメージをより具体化させていくことも多いそうだ。
「実は私はパフューマーになる前、脚本家や映画監督になりたかったんです。脚本家の資格を取ろうと思って、スクールにも通いました。そこでは、カフェで人間観察をして書き出すようなトレーニングもありました。そこで教師から絵コンテが上手だからと言われ、勧められるがままに映画監督の資格を取ったこともあります。当時は女性が就くのが難しい職業だったので諦めましたが、今でもいつか映画を撮ってみたいと夢見ています」
「香りをデザインすることも、対象をよく観察すること、連想することが大事になるので、共通している部分があるように感じます。絵を描くこと、文字を書くこと、写真を撮ることは、今でも大好きで続けています」
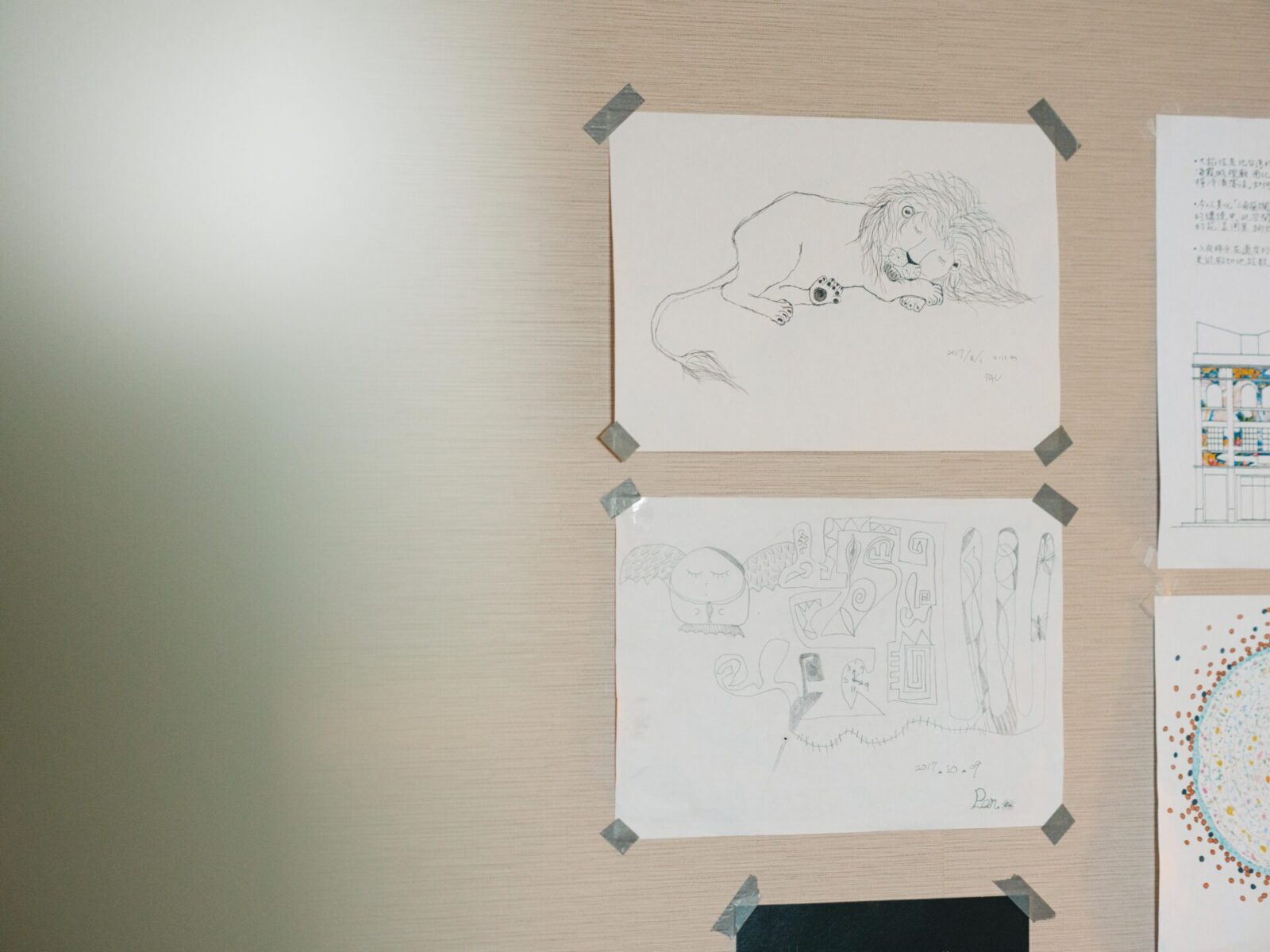
自然の中で過ごす時間も、Panさんにとっては五感を研ぎ澄ます大切なひとときだ。
「台北はすぐに大自然にアクセスすることができるので、よく森をハイキングしたり、海辺に行ったりします。故郷の花蓮にもよく帰ります。その場その場で感じた香りを、日記や写真で記録しています」
土地からブランドまで、あらゆる香りをデザインする調香哲学
土地やブランドといった、形のない概念をも的確に香りで表現するPanさんのデザイン力は評判が評判を呼び、さまざまなブランドからの依頼が後を絶たない。
最近では、火鍋の有名店から「火鍋の香り」を依頼されたこともあった。
クライアントのために香りをデザインするときは、Panさんはだいたい3種類のパターンを提案するという。ごくたまに修正が入るものの、修正に応じた香りを用意しても、「やっぱり最初に提案してもらった香りが良い」といわれることが多いのだそうだ。

自治体、空港、火鍋まで、香りをめぐる依頼は実に幅広く、またそれに対する印象も一人ひとり異なるにももかかわらず、なぜ、そんなに的確なデザインが可能なのだろうか。
「おそらく、香りをデザインする前に相当の準備をしているからだと思います。私がクライアントに提案する3種類の香りのパターンはそれぞれ、ブランドの立場からそのフィロソフィーを香りに落とし込んだもの、私個人の立場でそのクライアントをイメージしたもの、そして自分が消費者の立場に立ってデザインしたものです」
「ブランドや企業文化を理解するために、時間をかけてブランド創設者や従業員たちの話を聞きますし、消費者を理解するために、さまざまなことを想像します」
はたして、どんなことを想像しているのだろう。
「たとえば空港だったら、これから旅に出る人たちはどんなことを感じているのか考えます。そしてそれを、どのように表現するのかを考えます。飛行機に乗ることに対して期待が高鳴る人も、緊張する人もいるでしょう。では、その空間はどのような雰囲気であると良いのか。そういったことを連想していきます」
それでも、ごくたまに、オーナー個人の好みで修正が入ることもあるそうだ。「この原料を加えてほしい」「こういう方が好き」といった個人的な好みであっても、Panさんはそれをはねのけたりしない。
「そのブランドはオーナーのものですからね。私自身も『P.Seven』というブランドを経営していますから、そうした想いは理解できます。クライアントのために香りをデザインするときは『P.Seven』らしさは出しません」
「育った時代や場所が違っても、自分がデザインした香りを嗅いだ人が、同じようなものを連想してくれたとき、共感してもらえたときには、『良くできた!』と嬉しくなりますね」

台湾茶香水を通じて届ける「自分と向き合う時間」
日本でも販売を開始していたものの、品薄状態が続いていた「奉茶」シリーズは、パッケージ類を除く香水部分のみ日本で製造できる体制が整ったという。
「この香水を通して、台湾茶を淹れて飲んでいるかのような体験を日常に取り入れていただけたらうれしいです」と語ったPanさんは、インタビューの直後、日本出張へと旅立って行った。
台湾茶の魅力を「香り」で伝え続ける伝道師の自信作は、日本でも一人ひとりの「自分と向き合う時間」を創り出していくのだろう。


》「奉茶」シリーズの3つの香り
「Oolong Tea 沁香」【 一つの物語で語る、魂の一部分 】
ウーロン茶には、緑茶のような爽やかさと純粋さがある。ジャスミン茶のしなやかでほんのりと香るフローラルな香りに包まれ、爽やかな香りが高揚し、喉から鼻の奥へと香りの余韻を感じられるのは、まるで人里離れた山奥を彷徨っていると、偶然にもあたり一面に広がる秘密の花園を見つけた時のような麗しい喜びのよう。白紙の物語に、自分の魂を映し出すと世界の見え方が変わり、思わず微笑んでしまうのと同じかもしれない。
ベースノート:オリエンタルティー系
トップノート:フレッシュグリーン
ミドルノート:凍頂烏龍茶、ボタニカルフラワー
ラストノート:ハーブウッディ
香り:烏龍茶、ジャスミン、ゼラニウム、カシミールイトスギ
「Aged Tea 暗香」【長い歳月の息吹が凝縮した、台湾老茶の静かで豊かな魅力】
その衝撃は静かな時の中で強大に、草花をも呼び覚ます。お茶の香りは高貴で趣があり、後味には季節や大地の鮮明な声が隠される。
烏梅と龍眼の甘さがある静かで濃厚なスモーキーな香りが余韻を残し、木本来の香りと古来の知恵が包み込む。あの長い歳月は決して無駄なものではなかったと感じるだろう。
ベースノート:台湾老茶
トップノート:さわやかなハーブ系
緑茶、烏龍茶、青草
ミドルノート:オリエンタルティー系
紅茶、烏梅(梅の実を燻製したもの)
ラストノート:スモーキーウッディ系
ホウショウ、シダー(台湾杉)
香り:ウーロン茶,紅茶,綠茶,烏梅
「Formosa Beau-Tea 玉香」【 軽やかに弾けるシャンパンスパークリングにウールの柔らかさを加えて】
東方美人茶のしなやかで艶のある香りに、繊細なシャンパンフルーティーを加え、優しいカシミヤウールのようなムスクの香りへと落ち着いていく。
しなやかで艶のあるシャンパンフルーティーはグラスの中で軽やかに弾けて、ジャズを彷彿とさせるスパークリング感。フレッシュグリーンから黄金に輝く完熟フルーティーに変わる様子は、まるで純粋な少女から艶やかな女性に変わる様を描いているかのよう。それが柔らかく知性的なお茶の香り。それは、一度破壊されたからこそ生まれた、人々が魅了されるお茶の香り。ベースにあるムスクの香りは、少女から女性への変化と同じように、時間をかけて明白に。人を惹きつける香りはカシミヤウールのように、夜更けに優しく寄り添う。
ベースノート:東方美人茶
トップノート:爽やかなシャンパンフルーティー
ミドルノート:東方美人茶
ラストノート:ベルベッドムスク清新香檳果香
香り:ウーロン茶、緑茶、ホーリーフ精油、ハチミツ
写真:Jimmy Yang
台湾在住の編集・ノンフィクションライター。1980年福岡生まれ・茨城育ち。東京の出版社で雑誌やウェブ媒体の編集に携わったのち、2011年2月に駐在員との結婚がきっかけで台湾へ移住。現地デジタルマーケティング企業で約6年間、日系企業の台湾進出をサポートする。台湾での妊娠出産、離婚、6年間のシングルマザー生活を経て、台湾人と再婚。独立して2019年に日本語・繁体字中国語でのコンテンツ制作を行う草月藤編集有限公司を設立。雑誌『&Premium』、『Pen』で台湾について連載中。ブログ「心跳台湾」にも、台湾での暮らし、流行、子育て、仕事のことなど台湾の「いま」がわかる情報を執筆している。
『DIG THE TEA』メディアディレクター。編集者、ことばで未来をつくるひと。元ハフポスト日本版副編集長。本づくりから、海外ニュースメディアの記者まで。企業やプロジェクトのコミュニケーション支援も。岐阜生まれ、猫好き。
