嗜好品には、体をつくる栄養があるわけではない。
生命維持に必要不可欠ではないのにもかかわらず、全世界で嗜好品はたしなまれている。
嗜好品は、人間らしく生きるために、なくてはならないものなのかもしれない。
嗜好品や嗜好体験を考えることは、人間が生きるためには何が必要か、ひいては「人間という生き物とは何か」に迫ることでもある。
現代における私たちの嗜好品や嗜好体験を探究するために、文化人類学や歴史学者など様々な一線の研究者に話を聞く、連載「生きることと嗜好」。
今回は京都精華大学教授の斎藤光さんの研究室を訪ねた。
斎藤さんは京都大学理学部の出身ながら、学問の枠を超えて、戦前の「カフェー」文化や「モダンガール」など、大衆文化の研究でも知られている研究者だ。
生物学史・性科学史・近現代文化誌。
斎藤さんが学問を越境するその原動力は、「“人間”について、わかりたい」という思いにある。
そのひとつの切り口がカフェーに代表される「嗜好品・嗜好体験」だ。
(取材・文:吉川慧 写真:木村有希 編集協力:笹川ねこ 編集:呉玲奈)
学問領域を超えた研究、原点は京大時代の出会い
──もともと斎藤さんは京都大学で生物学を学んでいたそうですね。
はじめは理学部で生物学を学びました。ちょうどその頃、京大の人文科学研究所にいた桑原武夫さんが、「現代風俗研究会(現風研)」というオープンな研究会を開いていたんですね。
「風俗」とは、現代の日常生活という意味で、私たちの日々の暮らしに関わることです。たとえばファッションや食べ物、もちろんお茶やタバコ、お酒といった嗜好品に関する研究や議論もしていました。
ここではアカデミアの人以外も自由に参加し、さまざまなテーマについて議論していた。研究会の存在に興味を持って、僕も参加するようになったんです。

──斎藤さんは理学部の学生ながら、学問の枠を超えて現風研にも参加していた。
はい。学問領域の壁を「超える」ことについて、京大は寛容というか、それが「当たり前」ととらえる空気だったと思います。
日本の文化人類学の先駆者として知られる梅棹忠夫さんは、かつて「京大人類学研究会」(通称:近衛ロンド)というオープンな研究会を長い間やっていました。
「近衛ロンド」には、理系も文系も関係なく若手の研究者たちが集まっていました。のちに国立民族学博物館が生まれたときに梅棹忠夫さんが初代館長になったのも、そういった流れと関連していると思います。
僕にとっては、「現風研」が「近衛ロンド」みたいなものでした。学部生であろうが、大学院生であろうが、教員であろうが、出版関係の人であろうが、興味がある方は誰が来てもよかったんです。

──境界を超えて「知」が集まるような気風があったんですね。先生が社会学に出会ったきっかけは?
僕が社会学に興味を持ったのも大学1年のときでした。もともと理学部生だったこともあり、当時の僕は社会学、もっといえば人文学にそれほど興味がありませんでした。「世の中を考えるにはサイエンスで事足りるじゃないか? なぜ他のアプローチが必要なのか?」と思っていたくらいです。
でも、京大の教養部にいた社会学者の吉田民人さんの講義がとても面白くて、考えを改めました。「物事の考え方にはいろいろな視点がある」と気づき、学問に対する考え方もシフトしたんです。

いったいどんな講義だったのか。吉田さんは「過去にはカール・マルクスやマックス・ヴェーバーといった学者がいますが、それらを全部含めて乗り越えているのが私です」と、超大風呂敷を広げていたんです(笑)。
当然ですが、「マルクスを乗り越えている」という言葉に反発した左派系の学生からヤジが飛んで、吉田さんと議論になりました。
もちろん、吉田さんが議論で負けることはありません。学生の論の甘い点を指摘する。「あぁ、すごいな……」と。
そのすごさに圧倒されて、理学部なので必修ではありませんでしたが、吉田さんの講義はすべて出席しました。ノートも全部取りましたし、そこから広がって(フランスの社会学者)デュルケムなどの著作も読みましたね。

嗜好品は「社会的なものが折り重なっている」
──生物学から科学史、そして社会学へ。今では近代の大衆文化など、斎藤さんは人間の営みそのものに学問領域を広げています。
ずっと考えているのは「どんな切り口で考えると、“人間”について一番よくわかるのか」ということです。
たとえば、「霊感」という言葉がありますよね。最近話題の「霊感商法」という社会問題や、「私には霊感があります」と言う人もいたりします。
科学的な立場から考えると、そもそも「霊感」は存在しません。「霊感」は測定できないし、目に見えず、触れられませんから。
ただ、人間を取り巻く社会的なもの、共同的なものとしては確固として存在している。呪術やシャーマニズム、宗教とも近いものです。
人間を理解するには、自然科学・人文科学・社会科学、あらゆるアプローチが必要です。
社会学を勉強しようと思ったのも、そういう思いからでした。

取材をした京都精華大学のキャンパスでは、さまざまな学生が行き交う。
──嗜好品も、どんな学問領域から捉えるかで、見えるものが違ってくるものでしょうか。
そうですね。嗜好品自体は物質的なものです。とはいえ、科学的な立場からも、人文学的な立場からも、研究できますよね。
たとえば、コーヒーの味はどうでしょうか。どの物質が、どんな味を出しているかは科学的に成分を分析できます。
ですが、コーヒーを飲む「場」や「誰と飲むか」なども、個々人が感じる味に影響するのではないでしょうか。
単に物質に対する反応だけではなく、社会的なものが折り重なっている。嗜好品には、それが顕著に表れると思います。
私は、人間の身体性に関わる分野として、嗜好品に焦点を当てています。
カフェーの文化史。「場」から考える嗜好品と嗜好体験

──斎藤さんは戦前の「カフェー」文化について著書にまとめています。カフェーは、現在の喫茶店やカフェのルーツとされ、洋食や酒、ウェイトレスの給仕やジャズの演奏、ダンスを踊るハイカラな社交場として人気でした。戦争の影響もあって今ではほとんど姿を消しましたが、戦前は嗜好体験の「場」として存在感があったようですね。
飲酒には、ネガティブな側面だけではなく、楽しい体験もありますよね。嗜好の「場」だった「カフェー」にもそういう側面があったと思います。
楽しくお酒を飲んで、酔って、心地よかった体験。言うなれば「酔った作用の中にいる」と感じることは、日常から外れたもの。これを記憶だけで蘇らせることは難しい。
楽しかったけど、よく覚えていない体験がある。そこでもう一度、その楽しかった体験を求めて、人々は「カフェー」に通っていたのではないでしょうか。

──なるほど。記憶できない「楽しみの追体験」ですか。
酔うと記憶があいまいになる人は多いものです。酔った感覚から、ふと素面になった時、もう一度「酔う」という感覚を記憶から自己再現することは難しい。
楽しかった瞬間を再び求めるため、お店に何度も通って楽しむ……ということになるのかもしれません。
昔はカフェーでしたが、今では居酒屋やバーでしょうか。人々はお気に入りのお店をつくって、「楽しかった」瞬間を幾度も再現してきたはずです。
ただ、お店に通う人がいなくなれば、すべてが消えてしまいます。一人、また一人といなくなるだけならまだしも、店自体がなくなると、そこでの「体験」はすべて消えてしまう。
「カフェー」がそうですが、非日常の体験だからこそ、行ったことがある人が記した当時の記録そのものも少なく、今の私たちが追体験するのは難しい文化になってしまった。
──非日常における楽しみの体験は、場が消えるともに、たどることが難しいのですね。
残念なことに「カフェー」の文化は、いろいろな断片から回顧するしかありません。それが私がいま重点的に取り組んでいる、近現代文化誌の研究分野です。

「日常からの離脱」を求めて、人は嗜好品を愛する
──ちなみに、斎藤さんがお好きな嗜好品はなんですか?
一番関心があるのは、コーヒーとお酒ですね。「なぜ?」というのは難しいんですが……。
特にお酒は「日常からの離脱」ができるところがおもしろい。それが「酔う」という状態ですよね。
でも、「酔う」ことは案外難しいものです。「酔い過ぎる」といろいろと失敗するわけで。ダメになる手前というか、自律を持ちつつ絶妙なところに留まって「酔う」ことはとても難しい。
──初めてお酒を飲んだときのことは覚えていますか?
大学時代に京大・吉田寮の食堂で懇親会があって、すき焼きを食べた。そのとき、初めて燗の日本酒を飲んだと思います。
ただ、学生の飲み会ですからね。あんまりいいお酒じゃなかった。飲むと口の周りがベターってなって……。「おいしくない」というのが日本酒に対する最初の印象でした(笑)。
でも、後に冷酒を飲むようになると、「あれ? おいしい。ちょっと違うな?」と感じ、日本酒への印象が変わりました。今でも燗より冷でいただくことが多いです。
酒という嗜好体験はおもしろいものです。お酒を飲んでいるときはその時間がすべてで、日常から離脱できるのに、飲みすぎてしまうと記憶もあやふやで、楽しかった時間も消えていく。
そうして消えゆくものは、どうしたら研究できるのだろう?
私の研究のベースには、そういった自分の嗜好体験があるのかもしれません。

──こうしてお聞きすると、瞬間的な「楽しさ」に没入できるのも、嗜好品や嗜好体験の特徴かもしれません。
嗜好品から味わえる一つ一つの体験を覚えていなくても、なんとなくその瞬間が楽しかったという身体的な感覚は残っていますよね。
でも、まったく同じ体験はなかなかできない。それは「場」についても同じだと思います。
たとえば、久しぶりに通った道で店が潰れていることがありますよね。でも、「ここに何かお店あった」という感覚はあっても、何の店があったのか思い出せないことがあったりしませんか。
僕の著作『幻の「カフェー」 夜の京都のモダニズム』にある「幻」という言葉には、記憶には残っても消えてしまう。そんな思いを込めています。

──確かに。きっと世の中には、今あるお店以外にも、かつていろいろな人が楽しんでいた人やお店があった。でも、時代が変遷し、お店が消え、そこに通った人々もいなくなり、やがて「場」に関することはすべて消えていく。
嗜好品や嗜好体験は、過去や未来ではなく「今」という瞬間にフォーカスしています。とても刹那的・瞬間的であり、ある意味で動物的な構造になっているのだと思いますね。
どんな切り口で考えると、“人間”について一番よくわかるのか。
私は「嗜好品や嗜好体験」は、人間を解き明かす切り口のひとつだと考えています。
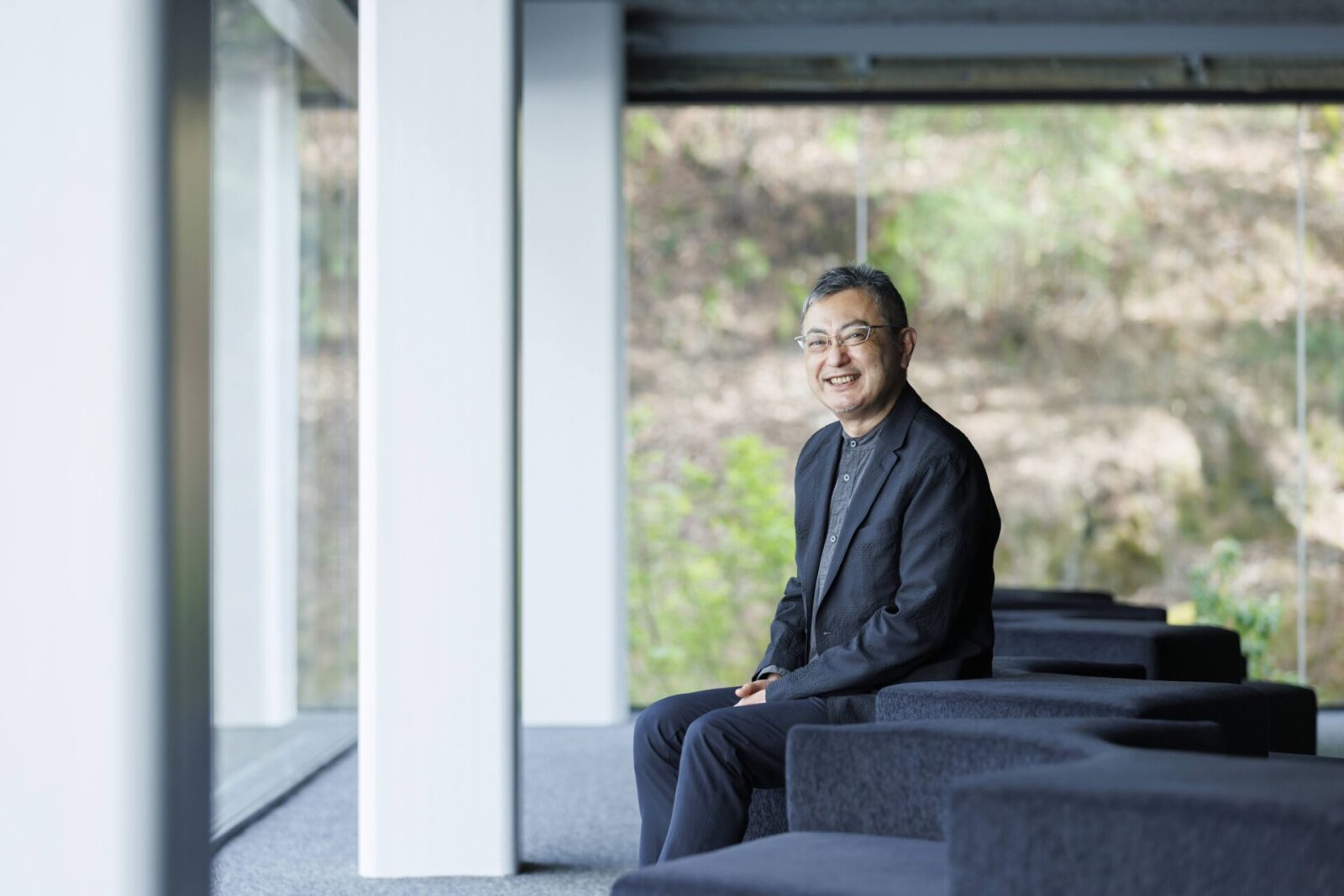
(後編「茶道とサウナの共通点——嗜好体験が「文化」になるとき:科学社会学研究者・斎藤光」は、5/29(月)に公開予定です)
Business Insider Japan記者。東京都新宿区生まれ。高校教員(世界史)やハフポスト日本版、BuzzFeed Japanなどを経て現職。関心領域は経済、歴史、カルチャー。VTuberから落語まで幅広く取材。古今東西の食文化にも興味。
Editor / Writer。横浜出身、京都在住のフリー編集者。フリーマガジン『ハンケイ500m』『おっちゃんとおばちゃん』副編集長。「大人のインターンシップ」や食関係の情報発信など、キャリア教育、食に関心が高い。趣味は紙切り。
『DIG THE TEA』メディアディレクター。編集者、ことばで未来をつくるひと。元ハフポスト日本版副編集長。本づくりから、海外ニュースメディアの記者まで。企業やプロジェクトのコミュニケーション支援も。岐阜生まれ、猫好き。
