世界各地の高級レストランに見られる「現代料理」。
レストランの位置する場所における、自然と文化の前衛的な解釈を試みる料理のことだという。
そんな現代料理を文化人類学の観点から研究するのが、東京外国語大学特任研究員で東京大学博士課程の藤田周さん。
藤田さんは、ペルーの世界的な現代料理レストラン「セントラル」(編注:2022年に世界のベストレストラン50で第2位、南米のベストレストラン50で第1位を獲得)などで約2年間、見習いとして働きながらフィールドワークを実施。料理人たちがどのように料理に取り組んでいるかを調査した。
一見すると洗練されたハイカルチャーのようにも映る現代料理だが、そのあり方を見つめることで、「家庭料理などの一般的な料理の見え方が変わる可能性も秘めている」とのこと。
現代料理とは一体何なのか。そもそも料理とはどのような営みなのか。藤田さんの研究と思索に迫った。
(文:篠原諄也 写真:田野英知 編集:小池真幸)
ローカルな食材で、新しい味を探究する
──あまり聞き慣れない言葉ですが、そもそも「現代料理」とは何でしょう?
フランス料理などの従来の高級料理をもとにしつつも、その枠を越え、レストランの位置する場所の自然と文化の前衛的な解釈を試みるような料理のスタイルのことを言います。

私がフィールドワークをしたペルーの現代料理レストラン「セントラル」では、料理ごとに海や砂漠、アンデス、アマゾンなどと地域を限定し、それぞれの自然の恵みを表しています。
たとえば、「赤い岩」と名付けられた料理。ペルーの標高マイナス10mにおける海岸の生態系を表していて、海岸の岩礁に育つカメノテや、ホヤの仲間で赤い身が特徴的なピウレといった海産物を使っています。

続いて「極限の高地」は、標高4350mのアンデスの農村の生態系を、色とりどりの在来種のとうもろこしを使って表現しています。
白とうもろこしで団子を、紫とうもろこしで泡を、赤とうもろこしでチップスを作り、とうもろこしの伝統的な発酵飲料を使ったソースも添え、さまざまな形や食感にしています。

──「標高」から料理を表現するのは斬新ですね。私たちは普段、味や色、旬などで食材の組み合わせを考えます。
この発想は、ペルーのローカリティと関わっています。
たとえば、アンデスの人々には、標高差で世界を捉えるコスモロジー(世界観、宇宙観)があるんですよ。「天界」「地界」「地下界」などと、垂直方向で世界が異なると考えている。
ペルーの、標高差によって海から砂漠、高山、熱帯雨林までエコシステムが全然違うという特性を、料理で表現しているんです。
──他の地域の現代料理にはどのようなものがありますか?
ペルー以外での代表例としては、現代料理を確立したレストランの一つであるデンマークの「ノーマ」における、「ハーブのブーケ、アリを散りばめたクリームフレッシュ」という料理がよく知られています。
北欧産のハーブやクリームフレッシュを合わせているのですが、そこに酸味があるものも欲しいと考えた時に、北欧ではレモンなどが採れないため、代わりに現地のアリを散りばめたんです。

現代料理には基本的に、ローカルな食材を使って、新しい食を味わわせてくれるという方向性があります。
食べられるものの可能性を拡大し、それがおいしくなるように味を引き出していく。そして、土地との関係を深めていくのです。
料理人はいつ「芸術家」になったのか?
──現代料理は、いつ頃からある料理のスタイルなのでしょうか?
2000年代後半から各国の高級レストランの一部で見られるようになったとされていますが、そこに至るまでにはさまざまな前史があります。
──前史、とは何でしょう。
そもそも18・19世紀のフランスで確立した「古典料理」においては、有名な料理家によって聖典化されたレシピがあって、料理人はそれを再現する職人のような存在でした。だから、新しい料理をつくることにはあまり価値が置かれていなかったんです。
それに対して、1960年代頃にフランスで登場した「ヌーヴェル・キュイジーヌ」という動向においては、料理人は料理を創造する芸術家として捉えられるようになります。
古典料理ではフォアグラ、キャビアなどが評価されていて、「新鮮さ」という評価軸がありませんでしたが、ヌーヴェル・キュイジーヌでは、早朝に市場で手に入れた食材を使うことに価値が置かれました。
当時、冷蔵庫が普及した社会背景とも連動しています。それまで低い位置に置かれていた野菜が評価されはじめるのも、この頃ですね。

──数百年の歴史をもつ古典料理を背景としつつ、20世紀後半に「料理を創造する」スタイルであるヌーヴェル・キュイジーヌが生まれたと。
そして1990年代頃になると、現代料理の最も重要な背景である、「モダニスト料理」と呼ばれる動向が生まれました。
代表例は、美食家のあいだで知られる、スペインのレストラン「エル・ブリ」です。このレストランでは、創造性や科学を意識した料理を提供していました。
有名なのは、脱構築された「生ハムメロン」。カクテルグラスの中に、メロンの果汁を人工イクラのように固めて、ハムのコンソメに浮かべたものなんです。初めて食べる人はキャビアのようでもありながら、カクテルのようでもある見た目に驚かされます。
おいしさだけではなく、驚きをつくるということ。「体験」という、新たな料理の価値を提供したんです。
こうしたモダニスト料理を背景に、2000年代に登場したのが「現代料理」なのです。

新しい料理は「組み合わせ」から創造される
──ここまで現代料理の概要や背景についてお話ししてもらいましたが、藤田さんのセントラルなどでのフィールドワークは、実際にどのようなプロセスで行っていたのでしょう?
いわゆる料理人見習いをしていました。
最初は食材の皮を剥く手伝いなどをしていましたが、次第に、盛り付けの作業を一緒にやらせてもらえるようにもなりましたね。料理人たちの手が空いている時は、料理や飲み物の試作を一緒にやらせてもらうこともありました。
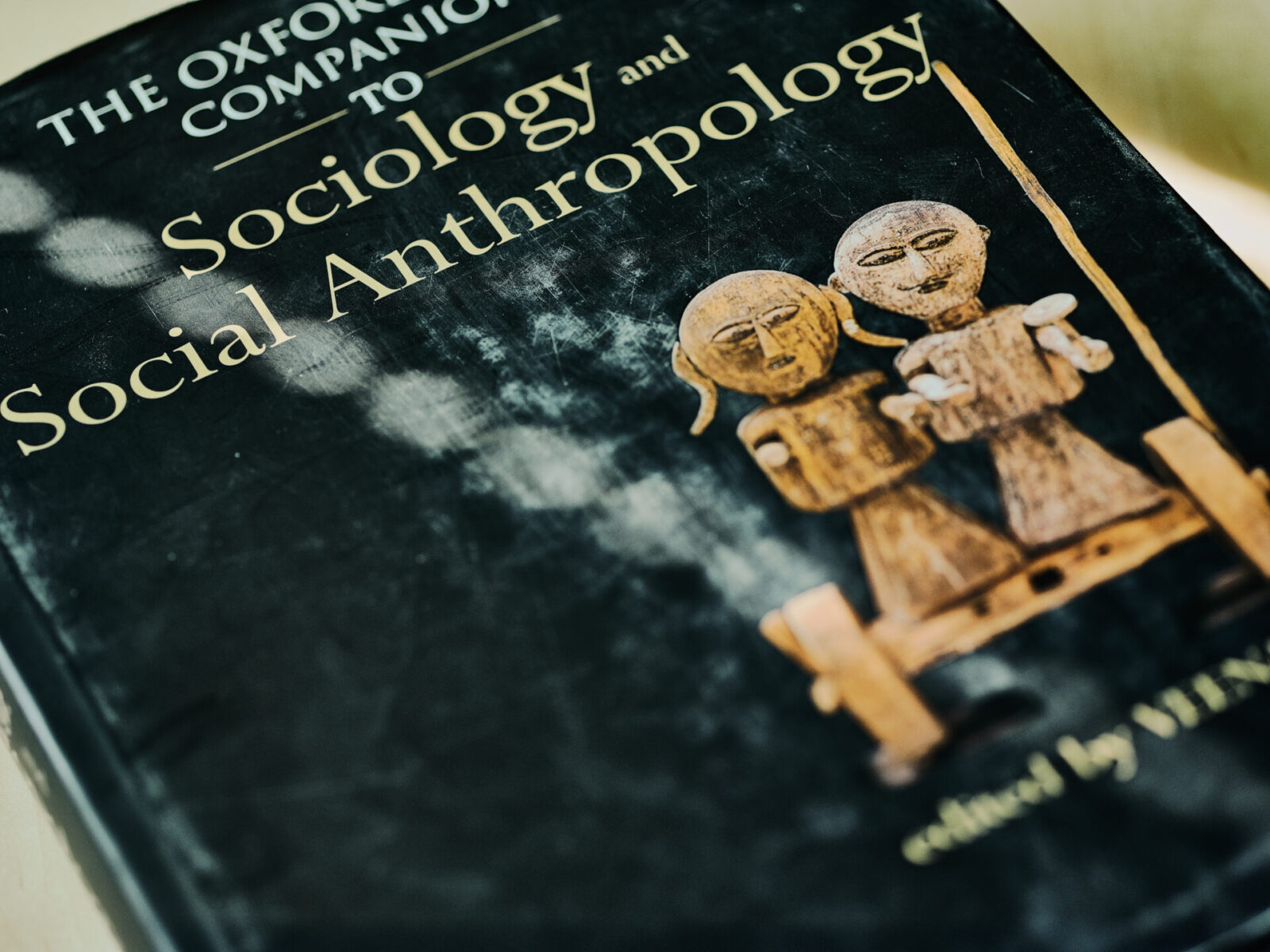
──見習いとして働きながら、料理人たちの思考や実践のあり方を明らかにしていったと。
はい。基本的に、料理人がしていることをすべて尊重するようにしていました。何でも面白がる、という方法論をとっていたんです。
大まかな方向性としては、現代料理の料理人が現場で何気なく考えていることを明確化することで、料理という行為に対する見方を拡張したいと思いました。たとえば、「いかにして新しい料理を創造しているのか」を見ていました。
──新しい料理、どういうプロセスでつくられていましたか?
ありあわせの道具、材料を用いて自分の手でモノをつくることを意味する「ブリコラージュ」をはじめ、「創造性とは組み合わせである」という考え方があります。
料理人たちもまさに、個々の食材がどんな味がするのかを覚えていて、それらを組み合わせる作業を常に実践していました。
たとえば、アマゾンレモンにコリアンダーを合わせる理由を聞いたら「この二つはなんか合う」と大まかな理由づけをしている。
聞き方を工夫しながら聞くと、「レモンとコリアンダーの香りが繋がった」と。つまり、レモンからある性質を取り出してきて、コリアンダーから同様に取り出した要素との組み合わせの良し悪しを考えているんです。
──そうした組み合わせを考え出せることが、料理人たちのいわゆる「天才性」なのでしょうか?
ひとつの食材にいろいろな性質を感じとっているので、ものすごい細かい知覚を持っている可能性はあります。
ただ、それが先天的な天才性かというと、私はそんな風にはあまり思えなくて。

レモンとコリアンダーを似ていると感じるのは、それらの組み合わせやレシピを無数に知っているからでもあります。
そもそもが天才であるというよりも、プロセスをたくさん積んでいるんですね。その経験があるからこそ、いろいろな幅を知っている。
料理の試作をしていると、失敗もあります。その中で「こんな風に焼くと、酸味が際立つのだな」など、食材についての学びが深まっていくんです。
天才性なのか、積み重ねなのか。どちらかを外すわけにはいきませんが、経験なしにうまくできている人はいない。そこはあまり区別できないと思います。
「ローカルとグローバルの対立」を超えて

──積み重ねか、ひらめきか。現代料理のみならず、あらゆる「創造」について共通するところがありますね
それからフィールドワークでは、セントラルの料理における、ローカルとグローバルの関係性についても考えていました。
両者は一般的に考えられているように、対峙するもの“ではない”と思っています。
ペルーでは2000年代半ばにガストロノミー運動が盛り上がり、国をあげて料理人たちを称揚したこともありました。それに対して、社会学者や人類学者から批判されたこともあったんですね。先住民系の人々には十分に利益をもたらしておらず、再開発による貧困層の立ち退きなど、悪い意味でのナショナリズムを生んでいるのではないか、と。
しかし、セントラルの人たちは、そうは捉えていないんです。
──どういうことでしょう?

彼らは、ローカリティの新しい表現を見つける方法を、グローバルに借りてくるということをしていました。グローバルな技術を使うことで、ローカルな食材の新たな側面を引き出せるようになることがある。
たとえば、セントラルの料理は、アンデス特有の料理というよりも、ノーマやエル・ブリに繋がるコスモポリタンな美学として捉えられますよね。それから彼らは「日本酒」の発酵の技法にも関心を示していて、それをペルーの食材に応用することができるかもしれないと考えていました。
お客さんも海外から多くやってきますし、ローカルとグローバルを対立させて捉えることはないんです。
ナショナリズムとは違う形で、ローカルなものを称揚する。それがセントラルの現代料理における、ローカルとグローバルのコスモロジーだと思います。

現代料理と家庭料理
──ローカルとグローバルの関係性も、あらゆる料理に通ずる議論のように感じます。思えば藤田さんは現代料理を研究対象としながら、日本の家庭料理などについても幅広く論じていますよね。
現代料理の料理人たちは、おいしさや食材に対して、一般的な感覚とは違う見解を持っていて、とても興味深いと思います。
なぜ私がそうした視点に重要性を見出しているのかといえば、それは料理人の見方を知ることで、普段私たちが食べているもの、そこでのおいしさや食材についても問い直すことができると考えているためです。
自分たちが当たり前だと思っている考え方を変えてくれる、もしくは私たちの前提条件の限定性を知ることに関心があるのだと思います。

──とはいえ、現代料理と大衆的な料理には明確な違いもありますよね。両者の差異や接点とは何でしょう?
まず違いは、現代料理はデフォルメされた形での料理が可能であることです。
すごく広くて清潔なテストキッチンで、さまざまな希少な食材を集めて、試作をすることができる。食材やおいしさについてじっくり考え詰めて、いろんな可能性を探ることが可能になっているんです。
しかし同時に、そうした希少な料理が教えてくれる知見を、大衆的な料理に活用し直すこともできるでしょう。
たとえば、家庭では希少な食材は手に入らないかもしれないけれど、おいしさや食材に対する考え方自体は、応用できるかもしれない。
また、私たちはある料理はこういう風につくるべきだとか、味付けはこうするべきだといった考え方を持っています。しかし、セントラルの料理人たちのようにそれを疑うことによって、食材の新たな味を引き出すこともできる。
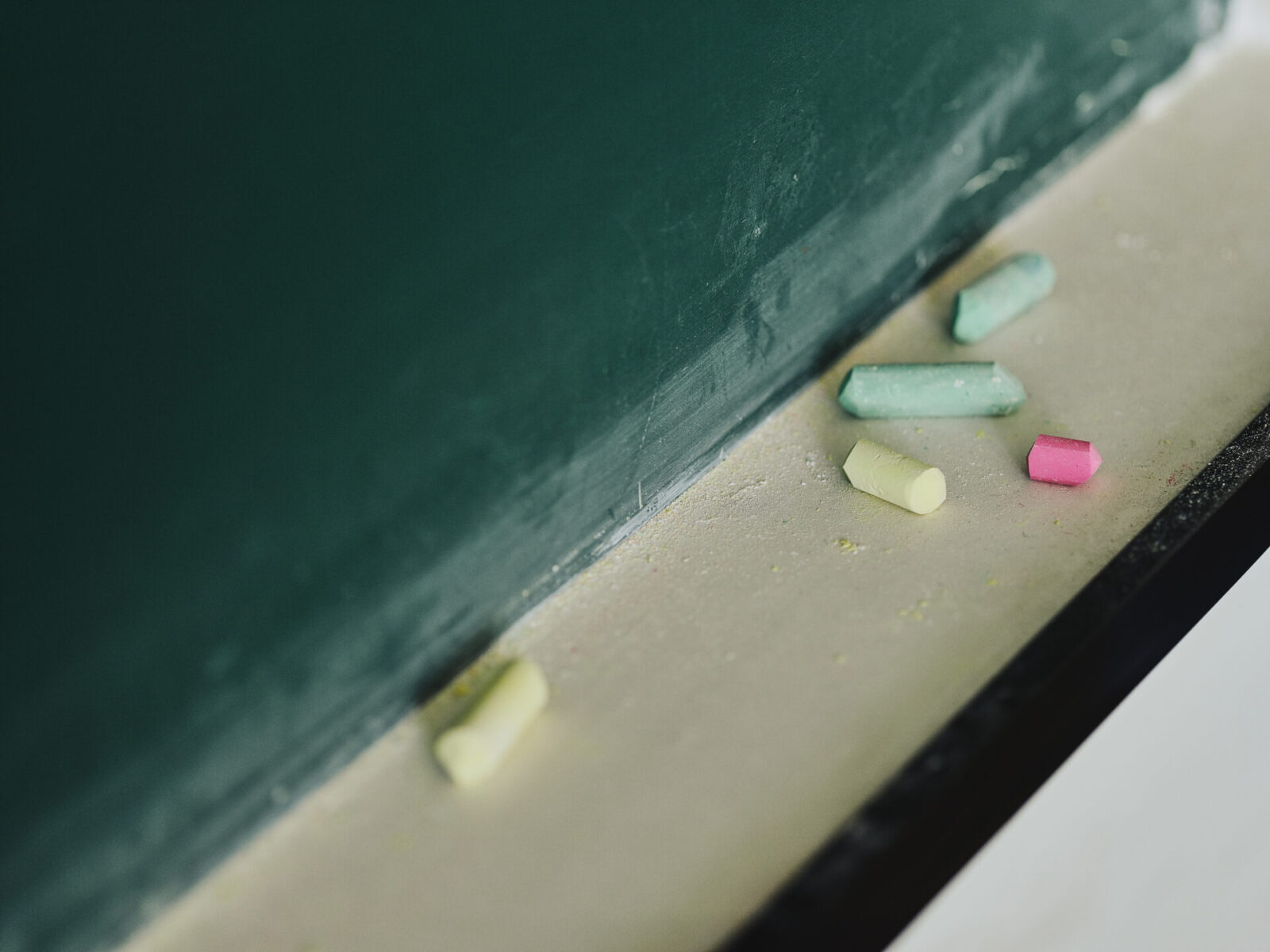
料理とは「問い」に答えること
──料理は生きるために必要不可欠なものではありますが、まさに現代料理は単なる栄養摂取以上の側面、言ってみれば嗜好品、時間芸術のような嗜好体験に近い性質もあるように思えます。
そうですね。嗜好品的な性質がないとは言えなくて、さまざまな条件次第で可能になるでしょう。
ただ、現代料理をもとに「料理とは食べ物をつくる以上のものである」と定義することを避けたくはあるんです。そのように定義すると、生活のために近所のスーパーで買った食材で、仕事や子育てに追われながらつくった料理は、何か本質が欠けたものとして見えかねませんから。

料理というのは、「食べるもの」にまつわるさまざまな問いに答えつづけてきた歴史なのだと思います。
「おいしさ」というのは欠かせない問いの一つです。そして「ローカリティ」にも縛られ続けている。毎日、体調やニーズを考えながら、「何を食べるのか」という問いに答え続けているんです。
──「問い」という表現は面白いですね。
現代料理の料理人がいろんな形で五感をひらくように、私たちも料理や食事をすることで、さまざまなことを知ることができます。
抽象的に考えるのではなく、実際に手を動かして料理をつくり、食べてみることで、如実に感覚が変わってくる。料理とは、世界に対する「感覚のひらかれ」を豊かにできる方法なのだと思います。

