「身の回りのあらゆるものが『嗜好』に満ち溢れている」
そう語るのは、 “究極の嗜好品”とも称される中東イエメンの嗜好品「カート」を研究する文化人類学者・大坪玲子さん。
カートとはエチオピアを原産とする低木で、その新鮮な若葉が嗜好品として消費されている。
お酒、タバコ、コーヒーなどは、生きていくために必要ではないけれど、人生の余剰として嗜まれているものと捉えられている。また、広辞苑でも嗜好品は「栄養摂取を目的とせず、香味や刺激を得るための飲食物」とされている。
しかし、そうした定義ではこぼれ落ちるものがある、と大坪さんは指摘する。
「そもそも、栄養摂取だけを目的とする飲食物はかなり少ない。栄養摂取そのものが目的かどうか、にこだわってもしょうがないだろうと思うんです」
大坪さんは、人類学者らによる嗜好品研究の論文集『嗜好品から見える社会』(春風社, 2022年)の編著者を務めた。
同書ではイランの水タバコ、トルコの酒、ペルーのチーズといった世界各地の嗜好品が、文化的・政治的・経済的観点などから多角的に論じられている。
「嗜好品から見える社会」とは、どのような風景なのだろう。大坪さんが研究する嗜好品・カートを起点に語ってもらった。
(聞き手・文:篠原諄也 写真:今井駿介 聞き手・編集:小池真幸)

嗜好品を“長年の呪い”から解放したい
──大坪さんの専門である人類学では、これまで嗜好品はどのように研究されてきたのでしょう。
人類学では嗜好品研究が盛んなのではないかと思われるかもしれませんが、実はこれまで全然行われてきませんでした。
そもそも嗜好品という言葉は、英語やフランス語をはじめほとんどの言語にはないので、国際的な研究が成立しにくいのです。日本語の嗜好品という言葉はドイツ語から翻訳されたもので、韓国語、中国語にも嗜好品という言葉はありますが、日本から輸出されたものだと思います。

そんな中でも、日本では学際的に嗜好品の研究が行われていました。それで2016年に、「嗜好品の文化人類学」という研究会を始めました。
研究会では、人類学者を中心に、自分のフィールドではこういう嗜好品があると発表してもらいました。人類学者は嗜好品を作るところから観察します。日本なら嗜好品はコンビニで買えますが、世界中がそういうわけではない。酒を造るところから始まる社会もあります。写真あり動画あり試食ありの発表で、研究会はいつも盛り上がりました。
そうした研究会やシンポジウムの成果をまとめてできたのが、この『嗜好品から見える社会』という本です。
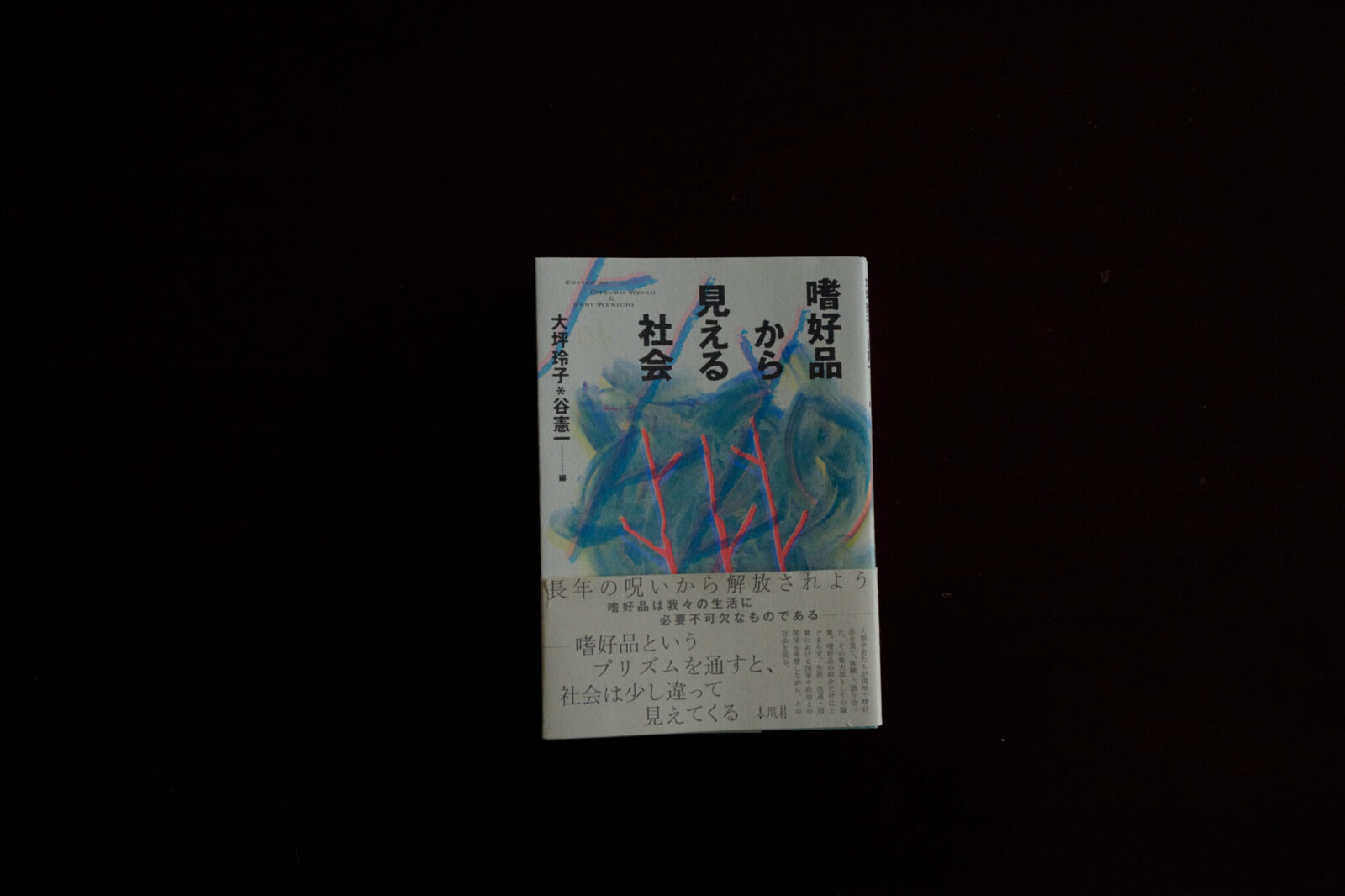
──本書の序論で大坪さんは「嗜好品を長年の呪いから解放したい」と書かれていましたね。つまり、「生きる上で必ずしも必要ではないけれど嗜まれるもの」という考え方に疑義を呈しています。
嗜好品の研究では、よく広辞苑の定義が使われますが、そこに「栄養摂取を目的とせず」とある。
でもよく考えてみると、普段の食事で栄養摂取を目的とする飲食物は少ないですよね。ですから、そこにこだわってもしょうがないだろうと思ったんです。
──たしかに。考えてみれば、「栄養摂取しよう」と考えてものを食べることは多くない気がしますね。
それどころか、実はビール、お茶、コーヒー、タバコなどの嗜好品は、栄養摂取を期待されることもあります。ビールは中世ヨーロッパではパンと並んで重要な栄養源でした。
それに限らず、アルコールは薬としての効果が期待されてきました。お茶やコーヒー、タバコも、消費が拡大するときは万能薬のように紹介されました。コーヒーは今でも「〜に効果がある」などという記事が出たりしますよね。
嗜好品であっても、人々は何かしら効用を求めたくなってしまうものなのかもしれません。それを考えても、「栄養摂取を目的としない」という表現はしっくりこない。
そこでこれまでの嗜好品の辞書上の定義は踏まえつつ、薬や薬物との境界は意識した上で、飲食物に限らず「身の回りのもののほとんどが嗜好に満ちている」ということを指摘しました。
同書で紹介されている嗜好品の中には、読者に「これは嗜好品なのか?」と思われるようなものもあります。先に説明したように嗜好品は世界共通の概念ではなく、あくまで日本語の嗜好品という概念を現地で当てはめたらどう見えるか、ということになります。執筆者がそれぞれのフィールドで嗜好品だと見なしたものが、同書で論じられています。
ただ、嗜好品の意味を広げるのはこれまでの日本の嗜好品研究でなされてきたことなので、同書のオリジナルではありません。
けれど身の回りのものをすべて嗜好品と呼んでしまうと、本来の意味での嗜好品がぼやけてしまうし、「○○は嗜好品である」「△△も嗜好品である」と新たな嗜好品の「発見」ばかりになってしまう。だから同書では「嗜好に満ちている」と書き、「嗜好品に満ちている」とは表現しませんでした。
いずれ嗜好品ではなく、嗜好に関する研究をしたいと考えています。人間に限らず動物の嗜好まで広げられたらと思います。壮大な研究になりますが。
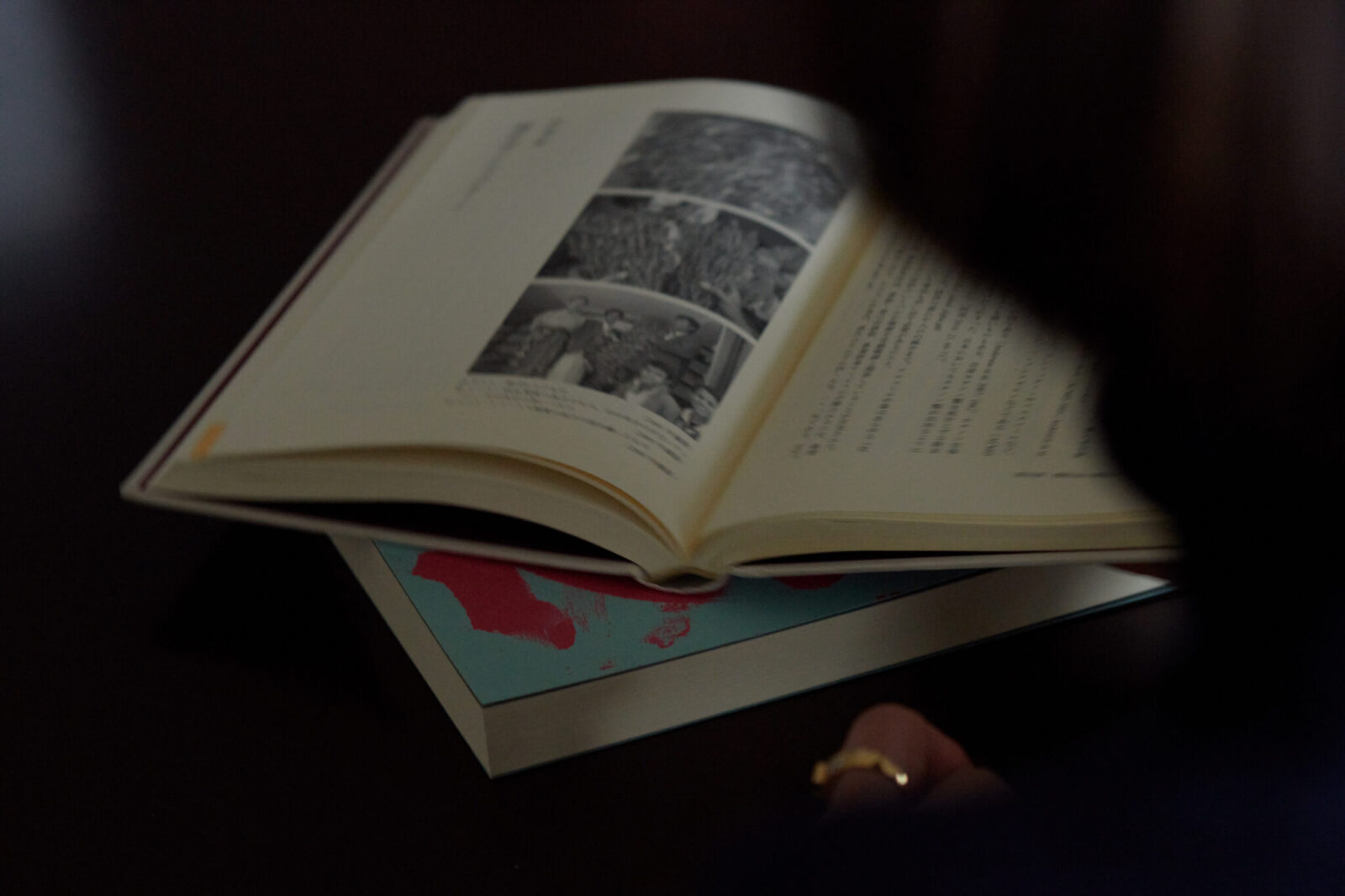
イエメン人に愛される嗜好品「カート」とは?
──大坪さんの研究対象である、イエメンの嗜好品「カート」についても伺っていきたいです。そもそもカートとは何なのでしょう?
カートはエチオピアを原産とする低木で、その新鮮な若葉はイエメンやエチオピアなどで嗜好品として消費されています。新鮮な葉にカチノンという成分が含まれており、噛むと軽い覚醒作用が得られます。
誰かの家に集まってお喋りしながら、お昼過ぎから3〜4時間ものあいだ、カートの葉を噛み、樹液は飲み込みますが、そのカスを片方の頬に溜めていきます。同時に水を飲むんですが、1リットル以上もの量になることもあります。一緒にタバコを吸う人もいます。
だんだんと葉のカスが溜まって、頬が膨れてきます。で、最後にトイレなどでペッと吐き出します。
他人の家で噛んだ場合は、自分の家に帰ってから吐き出します。イエメンの人は体によくないからといって飲み込みませんが、エチオピアではカスを頬に溜めず、噛んだら飲み込んでしまいます。

──カートはどのような味がするのでしょう?
一言で言うと、苦い。日本人の知人は、子どもの頃に間違って雑草を食べたときの苦さに近いと表現しました。
正直に言えば、日本にいて味が恋しくなることはあまりありません。カートを噛んで、午後をだらだら過ごすことは懐かしくなりますが。
──種類もいくつか分かれているのでしょうか?
イエメンの首都・サナアで出回っている形態は大体3種類です。葉っぱばかりのガタル、枝先30センチほどのルース、1メートル程度の枝を紐で縛ったルバトです。値段はガタル、ルース、ルバトの順に値段が高くなります。高いカートはそれなりに美味しいです。
ガタルは全部噛めますが、ルースやルバトの硬い茎や葉っぱは噛めません。だから廃棄分も多く、噛むのは新芽のところだけなので、すごく贅沢ですね。
毎日3〜4時間も。カートを噛みながらお喋りする、贅沢な時間
──イエメンの人々にとって、カートはどういう存在なのでしょうか?
イエメンは、娯楽施設が少なく、宗教上の理由で飲酒も禁止されているので、カートは老若男女問わず人気があります。
カートに年齢制限はありません。ただ毎日噛むようになるのは、男性なら一定の収入を得られるようになってから、女性は結婚してからです。私が調査していたころは、未婚女性は噛まないことになっていて、結婚すると「夫となら噛むの」というノロケを言いました。最近は未婚女性も噛むという噂を聞きますね。
カートに含まれる覚醒作用を求めているというよりは、誰かと一緒に噛んでグダグダお喋りをしたいんだと思います。誰かの家に集まって、カートを噛みながらお喋りをすることが多いですね。特にサナアの人は結婚式でもお葬式でも噛みます。
日本の「飲みニケーション」と似ています。つまり、酔っ払いたくてお酒を飲む人もいますが、お酒を飲むことが人と会う口実にもなる。サナアだと、ちょっと誰かと話したいときに「カートを噛まない?」と誘います。
──日本だと「ちょっと一杯どう?」「お茶しない?」みたいな感覚に近いでしょうか。ちなみに、みんなで集まって、何を話しているのでしょう?
1970年代に調査した民族誌を読むと、カートを噛みながら問題解決したり、人間関係を構築したりしたと書いてあります。部族間の紛争が解決されたときに、一緒にカートを噛んだという話もありました。私が調査したころはそれほど大袈裟なことはなく、ほとんどが日常会話、雑談などの些細な話でした。みんなでテレビを見ていることもありました。
そういう時間が毎日3〜4時間もあるのは、ものすごく贅沢ですよね。

── 毎日3〜4時間も。でも、そうなると仕事はいつしているのでしょう?
自営業だったら仕事中に噛む人もいます。チューインガムと一緒で、噛んでいると目が覚める。タクシーやバスの運転手、夜勤で働く人は噛みながら仕事をする。高校生や大学生はカートを噛んで試験勉強をするそうです。
また、イエメンの役所は午前中しか機能しません。だから公務員は午後からカートを噛んだり、副業をしたりします。外資系などの企業はカートは当然禁止なので、そういう職場で働く人は週末だけ噛むとか。
ある知り合いの女性は毎日午後、子どもを連れて実家に帰って、カートを噛んでいました。夫の運転で実家に帰り、お母さんやお姉さんとずっとカートを噛んでいる。その間、子どもたちはいとこ同士で遊んでいる。夕方になると夫が迎えに来て帰っていく。子どもは子どもで楽しいし、お母さんは気分転換できる。
イエメン人女性は、午前中に家事をやってしまいます。だから彼女も家事を終わらせてから実家に帰るわけです。カートばかり噛んで、家事も育児も放棄しているのかと考える方がいるかもしれないので、念のため。私も最初は彼女のことを批判的に見ていたのですが、そうじゃないんだと彼女の義姉が教えてくれました。
実際、イエメン人は仕事も家事も育児もしないでカートばかり噛んでいると批判する外国人はいます。しかし、午後中カートを噛んでいるだけのイエメン人はむしろ少数だと思います。

「カート売り」は社会のセーフティーネット?
──大坪さんはどのような観点からカートを研究してきたのでしょうか?
最初は消費の観点から追っていました。なぜカートを噛むのか、あるいは噛まないのか。どんな種類が好きなのか。そうしたことをインタビューやアンケートを通して調査しました。
その後、誰がカート商人になっているのか、どういう流通経路なのかなど、商人の調査を始めました。いくらで仕入れて、いくらで売っているか。カート商人は基本的に他の商品をカートと一緒に売ることはしません。それにカートは生産者から消費者の間に商人が1〜2人くらいしかいません。ですから、カートの流通経路を追うことも簡単でした。
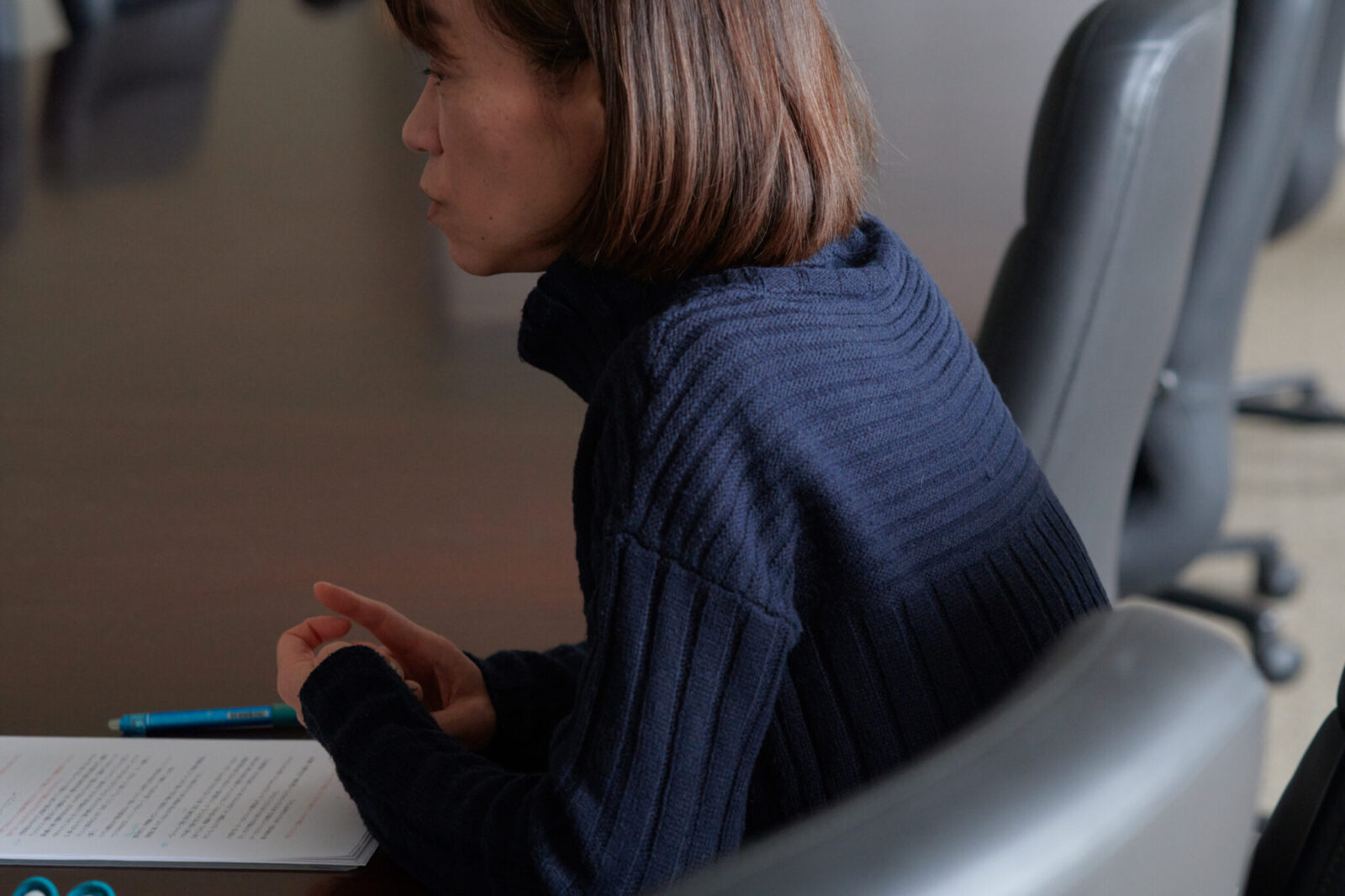
──カートはどのように仕入れがなされ、市場に出回るのでしょう。
サナアの商人は早朝に近郊の生産地に出向き、生産者からカートを仕入れます。そして昼前にはサナアに戻ってきて、カート市場で販売を始めます。客が来るのは13時前後で、15時を過ぎると客足は途絶えます。みなカートを噛む時間だからです。だからそのころから商人は安売りを始めて、仕入れたカートはその日のうちに売るようにします。
市場の中には売る場所が数種類あって、だいたい店舗と露天があります。店舗だと月極払いですが、露天は日払いなので、いきなり座って売り始めても誰も文句を言いません。後から場所代を徴収する人がやってくるので、そのときに場所代を払えばいいのです。
最近では、SNSも駆使しているようです。商人はInstagramにカートの写真をアップして宣伝したり、メッセンジャーアプリ・WhatsAppで客と連絡を取り合ったりしています。イエメンは2015年から内戦が続いていますが、ときどきInstagramにカートの写真が流れてきます。
カートは新鮮な葉っぱを摘んで、ビニール袋に入れると売れる。コーヒーはカートと栽培条件が似ていますが、コーヒーは収穫後に乾燥させたり脱穀したりと手間のかかる加工が必要です。
それと比べるとカートはかなり簡単です。カートが唯一の収入源で、それ以外は自給用の農作物を作るという生産者もいます。良いカートを栽培することは簡単ではありませんが、すぐに現金になるというのは、生産者にとってありがたい農作物です。
世界銀行の調査によると、イエメン人の7人に1人がカート関連の仕事に就いているそうですが、これは手軽であることが大きいでしょう。ライセンスは必要ないし、売る店舗を用意しなくていい。その日のうちに売り切ってしまうので、保管する場所もいりません。
だから数千円あれば、明日からでもすぐにカート商人になれる。仕事がない人は、ちょっとカートを売ってみようかな、となるんですね。

──カート売りになるためのハードルが、すごく低いのですね。
ええ。政府もほとんど規制しておらず、徴税は一応しているものの、脱税が多くてあまり機能していない。卸売市場もないし、大規模化するメリットがないので、農地を買い占めてカート畑にするような企業も私の知る限りありません。
みんな新鮮なカートを売りたいという思いだけで、毎日早朝からカートを仕入れて、昼前に市場へ売りに行く。それで十分に成り立っています。
──いつでも始められるという意味では、ある種の困ったときのセーフティーネットとなる仕事のような役割も果たしてもいるのでしょうか。
たしかに、そういう面はあるかもしれません。とりあえずカートを売れば、生活はどうにかなるという面はあるでしょう。
ただ商売を続けていくのは大変で、やっぱり上手い人と下手な人がいます。インタビューでは仕入れや売り上げの金額を教えてもらえましたが、けっこう差がありました。
サナアの商人は基本的に、カートを仕入れたらその日のうちに生産者に支払います。つけ払いはほとんどしません。何日か仕入れて、あまり品質がよくないなと思ったら、別の生産者から仕入れます。
それを浮気性と私は呼びましたが(笑)。信頼関係は大切だとはいえ、同じ生産者から仕入れ続けることは、商人としてはリスクが高いのです。客もカートの品質には敏感ですから。

品質は毎日変わる。現地の人々のカートへのこだわり
──そうして市場に出回るようになったカートは、どのように取引されるのでしょう?
お昼前後に市場に客がたくさん集まり、そこで商人と値段交渉をする。カートに定価も値札もありません。カートの産地を聞いたり、商人から手渡されたカートの匂いを嗅いだりする。ここで「味見をしろ」と言われることもありますが、味見はあまり良いマナーだとは考えられていません。
値段交渉は、「1,200」「900」「1,000」というように値段を言い合います(通貨単位はイエメン・リヤル)。大体1分くらいでしょうか。条件が合わなければ、客はすぐに次の店に行きます。

──カートを買う人々は、どんなことにこだわって選んでいるのでしょう。
先に説明した3形態と産地を組み合わせて買う人が多いです。「ハムダーニー(ハムダーン郡のカート)が絶対美味しい」「ニフミー(ニフム郡のカート)が好き」などと、産地によって味が変わるため、こだわりを持っている人はいます。
サナアの人はマイルド志向のようで、カチノンやタンニン(苦味成分)の少ないハムダーニーが人気があります。一方でニフミーは効果が強いカートと言われ、そこまで人気はない。他には水分量に違いがあり、水分が少ないものを好むのが通だと考えている人もいました。
ただそうは言いながらも、みんな自分の給料から計算すると1日分の予算は決まっているので、その範囲で買うようにしている。
イエメン人によれば、カートの品質は毎日変わるそうです。カートは新鮮な葉が一番なので、ストックしておいたらまずくなってしまう。だから毎日、市場をウロウロして、自分の予算と好みに合うものを探します。
それをやらないと、美味しいカート──つまり自分の予算内で自分の嗜好に合うカートということですが──は手に入らないんですよね。面倒くさいからその辺の商人から買おうとすると、自分の予算にも嗜好にも合わないカートになってしまうことも。
こう言うと、カート商人は客をだましてカートの値段を吹っかけてくると思うかもしれませんが、商人はそれほど悪人ではありません。だましたことがばれたら、翌日その客はもう来ませんから。
人付き合いにおける「無駄」の大切さ。イエメンのカートから学べること
──カートには嗜好品として楽しむだけでなく、いろいろな役割があるようですが、総じてどのような側面が大事だと思いますか?
誰かと話をするときに、カートのような嗜好品があると間が持つし、話が弾む。私自身、カートを噛みながらのインタビューはやりやすかったです。カートを袋から取り出したり、埃を払ったり、水を飲んだりするので、沈黙しても気にならないし、次の質問を考えたりもできます。
日本でも誰かと話すとき、何もないところでは話が続かないでしょう。お茶がないと間が持たないということもある。
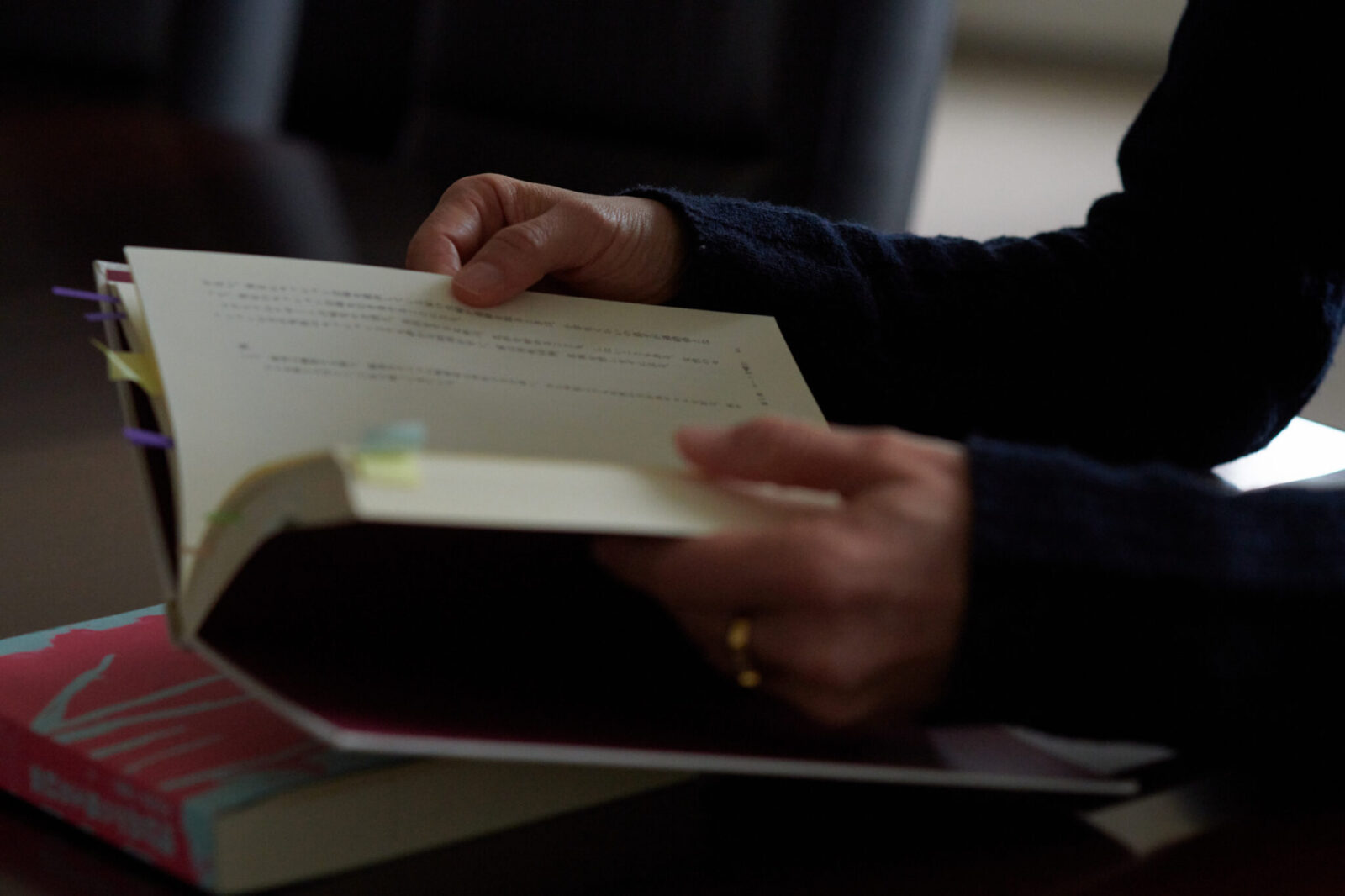
──カートは、コミュニケーションの媒(なかだち)としての役割が大きいと。嗜好品の重要な役割の一つですよね。
しかし、昨今、嗜好品は不遇の時代です。若い人はタバコやお酒に対して関心のない人も多い。タバコは広辞苑の嗜好品の例からもカットされました。
──日本企業を中心とした飲み会文化においては、そこに部下と上司などの権力関係があると不自由な場になってしまいがちですが、イエメンではどうですか?
イエメンでは、そうした側面はそんなに強くはなさそうです。
1970年代の調査を見ると、さまざまな社会階層からなる共同体の成員が集まって噛んでいたようですが、私が調査した2000年代のサナアを見る限り、そうした関係性はありませんでした。ほとんどが友達あるいは家族ばかりで集まっていました。
とはいえ結局、好きな友達だけで噛んでしまうのは、それはそれで閉じた空間ではあります。大体自分の家や友達の家でカートを噛むので、まったく知らない人と出会うというような開かれた場所でもありません。
──私たちは、イエメンのカートの文化、嗜好品の嗜み方からどのようなことを学べるでしょうか?
イエメン人は、人付き合いがうまいなと思います。「面倒くさいんだけれども、時間をかけてやらなきゃいけない」ということがわかっている。
日本では、「面倒くさいから人付き合いはしたくない」と言うことも可能です。
しかし、いくら面倒くさくても、ちゃんと電話したり、会いに行ったりして関係を作らないといけないということが、イエメンの人たちはみんなわかっている気がします。
だからカートが嫌いでも、午後の集まりにはいつも顔を出すという人もいる。
最近はコスパから派生した「タイパ」という言葉もありますね。それもいいけれど、人付き合いというのは、無駄がたくさんないとできないだろうなと思います。
そうした「無駄な時間」の大切さを、カートという嗜好品は教えてくれるのではないでしょうか。

》特集「嗜好を探求する」すべての記事はこちら
