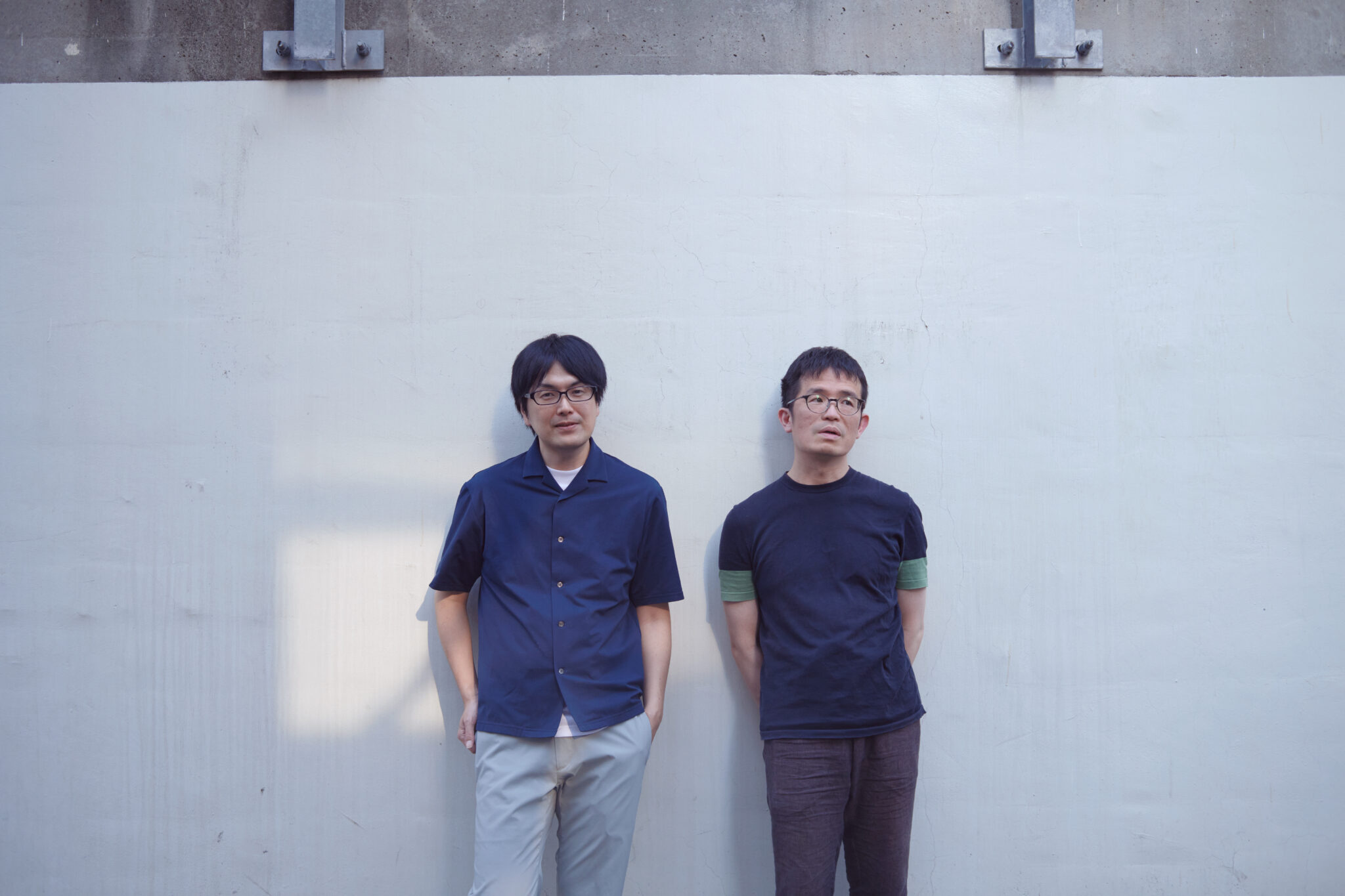飲み物、ことアルコール飲料は紀元前より「嗜好品」として人々に親しまれてきた。日本においては約2,000年前、稲作の定着と共に本格的な酒造が開始されたとされており、現在も嗜好品の一つとして確固たる地位を築いているように見受けられる。
しかし、徐々にその立ち位置は変化しているのではないだろうか。「あえて飲まない」ソバーキュリアスなライフスタイルが普及し、「酒=大人のたしなみ」という構図は少しずつ崩れつつある。現代を生きる私たちにとって、「酒」とはどのような意味を持つのか。また、ソバーキュリアスなライフスタイルの発現の背景には、時代のどのような変化が隠されているのだろうか。
この連載「『飲まない』大人の暮らし方」では、評論家・宇野常寛がさまざまな知見を持つ識者たちとの対話を通して、多角的に嗜好品としての酒の現在地や、「飲まない」大人のライフスタイルについて考えていく。
第5回にお迎えするのは、批評家で中国文学者の福嶋亮大氏。氏の専門である中国文学における酒の役割や、日本文学と酒の関わりを紐解きながら、いま私たちに求められている酒、あるいは嗜好品との向き合い方を探る。
(文:鷲尾諒太郎 写真:今井駿介)
飲みニケーションには「二重の中毒性」が存在する
宇野:福嶋さんは酒とどのように付き合っていますか?
福嶋:あまり酒が強くないので、日常的に飲むことはほとんどありませんが、国内を旅行するときは必ずその土地の日本酒を飲むようにしています。日本酒は、その土地の米や水でつくられていて、言うなれば土地と強い絆によって結ばれている。だから、その土地と身体的につながるぞという言い訳のもと、意識的に酒を飲むようにしていますね。

宇野:それはとてもいい酒との付き合い方ですね。福嶋さんとは付き合いが長いのでご存じだと思いますが、僕はもう10年以上、ほとんど飲まない。かつては付き合い程度に飲むこともあったのですが、いわゆる飲みニケーションの中で、とても嫌な思いをしたことがあって、それ以来まったく飲んでいません。
福嶋さんはいわゆる飲みニケーションについてどのように捉えていますか?
福嶋:飲みニケーションの根底にあるのは、日本の企業風土でしょうね。
たとえば、中国では「会社が終わってから同僚と飲みに行く」ことってあまりないみたいですね。友達と飲みに行くことはあっても、「同僚との飲み会」のようなものは少ない。昼に顔をつきあわせているのに、さらに夜も酒でつながろうとする日本人は、やはり特殊だと思います。もちろん、純粋に酒好きな者同士で飲みにいくのは一向に構わないんですけどね。
酒は本来「弱いつながり」をキープするのに向いていると思うんです。久しぶりに会う友人とは、やはり酒があると話がしやすい。あるいは大きな宴会にしても、ふだんは関係の薄い人たちとの絆をメンテナンスするのに有効なわけです。逆に、日本人の半強制的な飲みニケーションは「強いつながり」をもっとべったりさせるところがある。
では、なぜ日本では同僚たちとの飲み会が多いかと言えば、それはやはり社会人類学者である中根千枝が指摘した、ウチとソトを分ける「タテ社会」の問題でしょう。
企業が疑似家族的なタテ社会になって、メンバーを契約的というよりは感情的にくるんでいく。そのときに「飲み」が利用される。加えて、日本企業が長らく男性社会だったということも大きいと思います。
ちょっと面白いのは、霊長類研究者のロビン・ダンバーが『なぜ私たちは友だちをつくるのか--進化心理学から考える人類にとって一番重要な関係』の中で「人間関係のメンテナンスの方法は、男女で異なる」といった旨の指摘をしていることです。
ダンバーによれば、男女の間に知能などの差は見られないけれど、「どのように他者と関係を構築するか」は男女で差がある。
具体的に言えば、男性同士の場合「おしゃべり」ではなく「いっしょにいること」あるいは「共に体を動かすこと」によって、関係をつくっていく。二人並んで、黙って釣りをするとか(笑)。一方、女性同士は「おしゃべり」によって関係性を構築するらしい。もちろん、これも個人差はあるから過度な一般化はできないけど、面白い説だとは思います。
ダンバーのこの説を参考にすると、男性中心的な日本企業では「おしゃべり」が生まれにくかったのではないでしょうか。もちろん「共にいるだけ」でも、仲間意識は生まれるかもしれませんが、それだけでは仕事はうまくいかない。そこで、日本企業は言語的コミュニケーションを強制的に活気づける「飲み会」を求めたのではないかと思うんです。それは男性の言語コミュニケーションの弱さを補うという機能があったのではないでしょうか。
宇野:これは企業に限ったことではないかもしれませんが、「飲みニケーション」というのは泥酔する時間を共有することで、「本音」も共有しているのだと思うんです。素面では「建前」しか言わないけれど、飲酒すると「本音」で話せる。だからこの場を共有しているメンバーが共同体の一員だ、という確認ができる。
そういったコミュニケーション様式をインストールし、それに慣れてしまった結果、それ以外の方法を忘れてしまった人もいるように感じるんです。そのため、ムラ社会の「空気の支配」以外で集団の秩序が維持できなくなってしまっている。つまり、「飲みニケーション中毒」になってしまった。

福嶋:そうかもしれない。過度な飲酒を続けるとアルコール中毒になってしまう危険があるけれど、「酒の使い方」にも中毒性があるということですね。
宇野:飲みニケーションには「二重の中毒性」があるのだと思います。
「国風文化」とは、「酒を排除した文化」である
宇野:先ほど、中国の飲酒文化に少し触れました。福嶋さんの専門である中国文学における酒の存在や扱いを聞くことを通して、相対的に日本文化における酒について考えてみたいと思っているのですが。
福嶋:中国文学は「酒と共に歩んできた文学」だと言ってもいい。それほど、中国文学において酒は不可欠です。
そのパイオニアとして重要なのが、『三國志』で有名な曹操や竹林の七賢です。
曹操は日本では軍人政治家として知られているけれども、息子の曹丕や曹植とともに優れた詩人でもあった。曹操の「短歌行」は陣中の酒席で詠まれたと言われるけど、「酒に対してまさに歌うべし、人生いくばくぞ」という有名なフレーズがあって、人生や世界への感慨を、酒を前にしてぐっと濃く深めていく感じがある。曹操は酒と詩と戦争を強く結びつけた政治家です。逆に、その同時代の「竹林の七賢」はヒッピーみたいな連中だけど、やっぱり酒と薬で文学的な想像力をドーピングしたところがあるわけです。
三国時代の詩人たちの面白さは、酒とか薬を背景にして一種の「文学革命」を引き起こしたことにあります。これは作家の魯迅が強調したことだけど、彼らの登場によって、文体やレトリックが簡素になって、そのぶん思想が自由でのびやかになった。言葉づかいをシンプルにすることによって、むしろ複雑な思想を詩に込められるようになる。そういう意味での「革命」ですね。
それは感情表現を一面的にせずに、奥行きを与えたということです。もともと、漢詩は対句的なものだから、日本の和歌よりもずっと立体的に構築されている。
中国の詩では全般に、酒は「感情の立体化」に使われている気がしますね。実際、酒を飲むと、気分が高揚したと思いきや、急に沈むこともあるわけです。三国時代の詩人はそういう酒の抑揚を利用して、シンプルな言葉づかいでありながら、起伏に富んだ立体的な詩を生み出したってことでしょう。
ただ、日本にも一応その影響はあるんです。「酒と共にある文学」を日本に取り入れようとしたのが、『万葉集』を代表する歌人の大伴旅人です。
宇野:つまり、7世紀から8世紀にかけて、文学に酒という要素を取り入れようとする動きがあった?

福嶋:そうですね。ちょっと誇張して言うと、大伴旅人は中国の詩人のコスプレをしたわけですが、それにはやはり酒を文学に導入しないといけない。実際、『万葉集』には酒を称える旅人の歌が収録されています。ただ、それは自覚的なシミュレーショニズムというか、半分はギャグでもあるんですね。「私は酒壺になりたい」という歌があるくらいだから(笑)。
「令和」の元号のもとになった大宰府の「梅花の宴」の歌もそうだけど、大伴旅人はいわばジャズの即興演奏のように歌を詠むことを試みたわけですね。酒と場の力を借りたインプロビゼーション(即興)です。歌の作り方としては実験的なんですが、そういった彼の試みは、次の世代の歌人たち、具体的には『古今和歌集』(905年)の編者である紀貫之らによって排除されたんじゃないかと思いますね。

宇野:『古今和歌集』の時代に「酒」の文化が一度衰退した?
福嶋:『古今和歌集』には酒の歌がほとんどないんじゃないかな。少なくとも、旅人みたいに宴会のシチュエーションと歌をつなぐような中国的な詩人はいない。中国風の「酒と共にある詩」は、『万葉集』で一瞬出てきてすぐに終わってしまった気がします。
『古今和歌集』は国風文化の象徴だけれども、裏を返せば「国風文化とは、酒を排除した文化である」とも言える。
宇野:漢字と一緒に酒を忘れてしまったわけですね。
福嶋:僕の解釈だと、紀貫之は日本で最初の「ソバーキュリアスな文学者」なんですよ。
紀貫之は旅人的な酒の文学を排除して『古今和歌集』を編集しました。その結果、非常に理路整然とした美学的なデータベースともいえる歌集になった。三島由紀夫は『古今和歌集』を高く評価していたけれども、それも「数学の定理」のような古典主義的な秩序があるからです。
宇野:『万葉集』にあったある種の猥雑さを排除して、論理的な美しさを追求する流れがこのとき発生したわけですね。
福嶋:そうですね。あと、曹操や竹林の七賢、あるいは中国の代表的な詩人である陶淵明や杜甫や李白は、もちろんただの酒飲みということではなくて、みな広い意味での「思想家」でもありました。中国の詩人たちにとって「詩を作ること」は「思想を深めること」と同義です。
紀貫之はすごく優秀な批評家・編集者で、それ以降の日本文化は彼の作成した美学的データベースに沿って形成されたわけです。でも、彼は詩の思想性を、酒と一緒に排除してしまったのではないかとも思うんですね。詩と思想を結ぶ回路は、紀貫之の時代に断ち切られてしまったのではないでしょうか。

日本文化は、酒を取り込むことに失敗し続けている?
宇野:中国の詩人たちは、「自らの世界を構築すること」に酒を利用していたのではないかと思うんです。つまり、酒すらも自らの「現実」に取り込むことによって、その現実を作品に昇華していった。
対して、紀貫之以降、日本では「現実」、言い換えると「表の世界」あるいは「建て前の世界」から酒を排除してしまった。そうして、「裏の世界」つまりは「本音の世界」に酒を押し込めてしまったのではないかと。
だからこそ、今でも酒が「本音を引き出す道具」として利用されているような気がします。もし、紀貫之が酒を排除せず、「表の世界」に酒を組み込む選択をしていたら、日本人の酒との付き合い方も変わっていたのではないでしょうか。
福嶋:そうかもしれません。中国の詩人たちは酒を愛しているとはいえ、泥酔することを良しとはしない。孔子も『論語』で「乱れるまで飲んではいけない」とはっきり言っていますからね。
一方、日本の飲み会では、ベロベロになって「普段言えないことを言う」といったことが美徳とまでは言いませんが、変な慣習みたいになっている。道端で酔いつぶれたりとか、それは普通に考えれば異様なんだけど、都市風景の一部になっている。酒を破壊的な道具として使うのは、かなりおかしいと思いますね。
宇野:「泥酔する」ということは、酒を味わっていないんですよね。しっかりと味を楽しもうと思ったら、泥酔するわけにはいきませんから。
福嶋さんが旅行先でその土地土地の日本酒を飲むとき、間違いなく日本酒を味わっていると思うんです。そして、その目的を「その土地とつながること」とおっしゃったように、福嶋さんは日本酒の味を、自らの現実世界に反映しようとしているわけですよね。つまり、日本酒を味わうことを通して、自らの世界を構築しているのではないかと。それはソーシャルなレベルでの共同性の確認、つまり飲みニケーションとはまったく違うなにかですよね。

福嶋:そうですね。土地を味覚で体験する感じなので、ソーシャルな要素は皆無です。
あと、紀貫之に戻ると、やはり彼は詩を美学的記号にしたという面があると思うんです。その記号化のなかで『土佐日記』のようにジェンダーを取り換えるゲームをやる。日本的な美のデータベースというのは、実人生とはいったん切り離されるんですよね。
でも、杜甫とか白居易の詩というのは、彼らの思想書でもあるし、彼らの自伝でもある。中国の詩人たちは、酒の力を利用して感情の起伏を喚起すると共に、人生についての考え方を詩に込めた。対して、素面の状態を保っていた日本のソバーキュリアスな歌人たちは、歌をとことん美学化した。そしてそれが、日本文学の王道になった。
でも、そうすると「現実」や「人生」を歌には収容できなくなる。その受け皿となったのが、『平家物語』とか説経節(中世末から近世にかけ流行した芸能の一つ)みたいな「語りもの」の芸能でしょう。ひたすら美学的な洗練を追究する歌があり、そこからはみ出す過剰なもの、おどろおどろしいものは物語に回収される。ただ、この二極化が日本の文芸の弱点になった気もするんですね。
かなり時代が下って、戦後の混乱期に坂口安吾をはじめとした無頼派の作家たちが登場し、酒や薬と文芸が結びついた時期もありました。ただ、基本的に日本は酒をうまく文化に取り込むことに失敗したのではないかと思います。それがめぐりめぐって、いまだに泥酔したがる大人とか、旧態依然とした文壇カルチャーをつくり出している。
カフェは「仕事の効率を上げるツールを買う場所」になった?

宇野:日本では若者が酒を飲まなくなったといわれていますが、中国でも状況は同じなのでしょうか?
福嶋:どうもそうみたいですね。もともと、中国人はかなり派手な飲み会で、客人をもてなすということをやる。これはいわゆる「ポトラッチ」(客を迎え入れる側の者が、自らの地位と財力を誇示するために盛大な宴会を開催する習慣)に近いもので、昔の日本企業の駐在者は中国ではまず大量の酒の洗礼を浴びることになっていた。
この場合「もてなすこと」と「支配すること」は不可分であり、酒は平和のための道具にもなれば、他者を支配する武器にもなることを示しているという意味で、興味深いんですけどね。
とはいえ、その中国でさえ、若者の酒離れが進んでいると聞きます。
その理由はさまざまでしょうが、一つには「素面であること」「覚醒していること」に価値があるという風潮があると思うんです。
それは日本でも同様で、今後の先進国では居酒屋は減っても、カフェはなかなか減らないのではないか。時代を象徴する飲み物があるとしたら、21世紀は明らかに酒ではなくコーヒーの時代でしょう。
コーヒーは覚醒のための飲み物ですよね。ヨーロッパでは17世紀頃にコーヒーが飲まれるようになり、18世紀にはイギリスを中心にコーヒーハウスが流行しました。これは合理的な世界観を説く啓蒙主義が流行した時期でもあります。カフェインの効果で人工的に覚醒状態をつくり出すコーヒーは、産業社会における企業の発展や、経済合理主義的な考えとうまくマッチして一般化することになったわけです。
そして、コーヒーハウスには芸術家や文化人たちが集まるようになり、談話文化が花開いた。ローレンス・スターンとかディドロらの18世紀の小説はかなり饒舌だけど、それはどうやらコーヒーハウスのおしゃべりが反映しているみたいですね。ハーバーマス的に言うと、コーヒーハウスやカフェの自由な談話空間こそが、ヨーロッパの「公共性」のモデルということにもなる。
ただ、現在のカフェは誰かとの対話を通して、思想を育てる場所ではないですよね。コーヒーも結局「仕事の効率を上げるためのツール」になっているのではないでしょうか。

宇野:「飲む」ものは、ある意味食べるものよりも仕事だったり、社交だったり、他の行為と結びつきやすい。それだけに「飲む」という行為から社会的な「活動」のスタイルに介入できる。たとえば僕はスターバックス的なものの意味って、そこにあったと思う。
福嶋:かつてコミュニケーションを喚起し、思想を磨くための場所だったカフェは「仕事の効率をあげるためのツールをテイクアウトする場所」になってしまった。と、僕も偉そうに言うけど、結局は日々カフェでむりやり覚醒しながら原稿を書いているわけで、十分カフェイン中毒なんですけどね。
ともかく、その背景にあるのは「覚醒し、何らかの活動をしていることが重要だ」という価値観なのではないかと思うんです。
もちろん夜な夜な酒を飲んで、酩酊するのがいいとは言いませんが、「前近代的で不真面目なアルコール」と「超近代的で真面目なコーヒー」という二項対立を超える必要があると思うんですよね。
自らのとって必要な「自然」をガーデニングしながら生きる
宇野:「覚醒していること」の価値が高くなっているのは間違いないでしょうね。いまや老若男女を問わずSNSに夢中ですが、SNSは明らかに日常的な覚醒装置です。SNSを見ているだけでも脳は刺激されますし、炎上騒ぎを見れば脳はさらに興奮状態になっているはず。
僕は「ポスト酒」の嗜好品は、カフェインとSNSだと思っています。福嶋さんの言う通り、その背景には「覚醒していることが価値である」という考えがあると思いますが、その考え自体を批判的に見る必要があるのではないでしょうか。

福嶋:今後、基本的に酒が大規模に復権することはないと思うんです。先進国だとZ世代を中心に酒離れが進んでいると思いますが、そうするとZ世代は「アルコールを不要にし始めた最初の世代」として記憶されることになるかもしれません。
人類と酒の関係を考えると、今は大きな転換点だと言えるのではないでしょうか。
ただ、「素面である」ことは別に無条件で良いわけではないんですね。そもそも、醒めているからといって、正確に自分を認識できるわけではない。自己認識って基本的に誤るものなんですよ。
酒を飲むことのメリットの一つは、日頃の自己認識の誤りを突きつけられる、ということだと思います。自己がいかに不安定で危うい存在なのかを明らかにする手段としては、とても有効だったのではないかと。
だから、そういった誤りに気付くきっかけを排除して、クールで素面の状態にいると思い込むと、かえって足をすくわれてしまう気もするんですよね。宇野さんが今言ったとおり、覚醒してスマホを睨みながら、日々の情報に右往左往するソバーキュリアスなユーザーだって多いでしょう。
要するに、人工的な覚醒と理性はイコールで結ばれているわけではないんです。とはいえ、アルコールによって自己認識の危うさに気付く、というのは一昔前の文学的なアプローチでしかないでしょうね。その代替手段をどこに見出すかがポイントだと思います。
宇野:かつて、中国の詩人たちが酒を取り入れながら自ら表現スタイルを確立した。対して、僕たちはいま何をどのように取り入れてライフスタイルを構築するのするのか。それを再検討すべきフェーズに来たのかもしれません。

福嶋:たとえば、19世紀アメリカのヘンリー・ソローは、自然と一体となるような生き方を理想としていて、実際に森の中で生活し、散歩することによって思想を深めた。つまり、ソローは酒を飲むことではなく「歩行」を思索の手段にしていたわけですね。
もちろん、ソローのように森の中で生活を送るのは難しい。僕には絶対無理です(笑)。ただ、人間は自分一人の覚醒の力だけでは思考を深めることはできず、何らかの伴侶を必要とするのは間違いない。
18世紀のイギリス人にとってそれはコーヒーやコーヒーハウスに集う他者だったかもしれないし、中国の詩人たちにとってそれは酒だったのかもしれません。しかしいずれにせよ、思索を「昼のカフェ」と「夜の居酒屋」だけに閉じ込めてはならないと思います。
宇野:エマ・マリスは『自然という幻想:多自然ガーデニングによる新しい自然保護』で、ソローの言う「ウィルダネス」、つまり「手つかずの自然」なんて幻想だと指摘したことで知られています。そして、「人間はそのときに自らが必要とする『自然』をガーデニングするしかない」といった旨の主張をした。
ここでマリスが言いたかったのは、「人間は自らを取り巻く環境を、自らの手によって構築しなければならない」ということだろうと思います。つまり、かつてソローが「自然」を求めたように、現代を生きる私たちも環境を自分で「つくる」しかない。
僕たちはそれぞれが置かれた場所において、さまざまなことを自らの世界に取り入れて、自らの世界をコントロールし、現実をつくり変えながら生きていくしかない。その際、重要になるのは、“酩酊”と“覚醒”のいずれかに偏りすぎず、うまくその間でバランスを取ることなのかもしれません。