嗜好品には、体をつくる栄養があるわけではない。
生命維持に必要不可欠ではないのにもかかわらず、全世界で嗜好品はたしなまれている。
嗜好品は、人間らしく生きるために、なくてはならないものなのかもしれない。
嗜好品や嗜好体験を考えることは、人間が生きるためには何が必要か、ひいては「人間という生き物とは何か」に迫ることでもある。
現代における私たちの嗜好品や嗜好体験を探究するために、文化人類学や歴史学者など様々な一線の研究者に話を聞く、新連載「生きることと嗜好」。
前編の「1杯10円のコーヒーを奢り、奢られる。嗜好品が生む、タンザニアの“対等”な人間関係」では「嗜好品が、対等な人間関係を築くのに役立つ」と教えてくれた小川さん。
後編では、はたして「贈与」が彼らの社会でどのように機能しているのか。日本に暮らす私たちはそこから何を学べるか。そして嗜好品は、人間関係や社会にどのように寄与するかを掘り下げていく。
(取材:鈴木陸夫 写真:入交佐妃 編集協力:笹川ねこ 編集:呉玲奈)
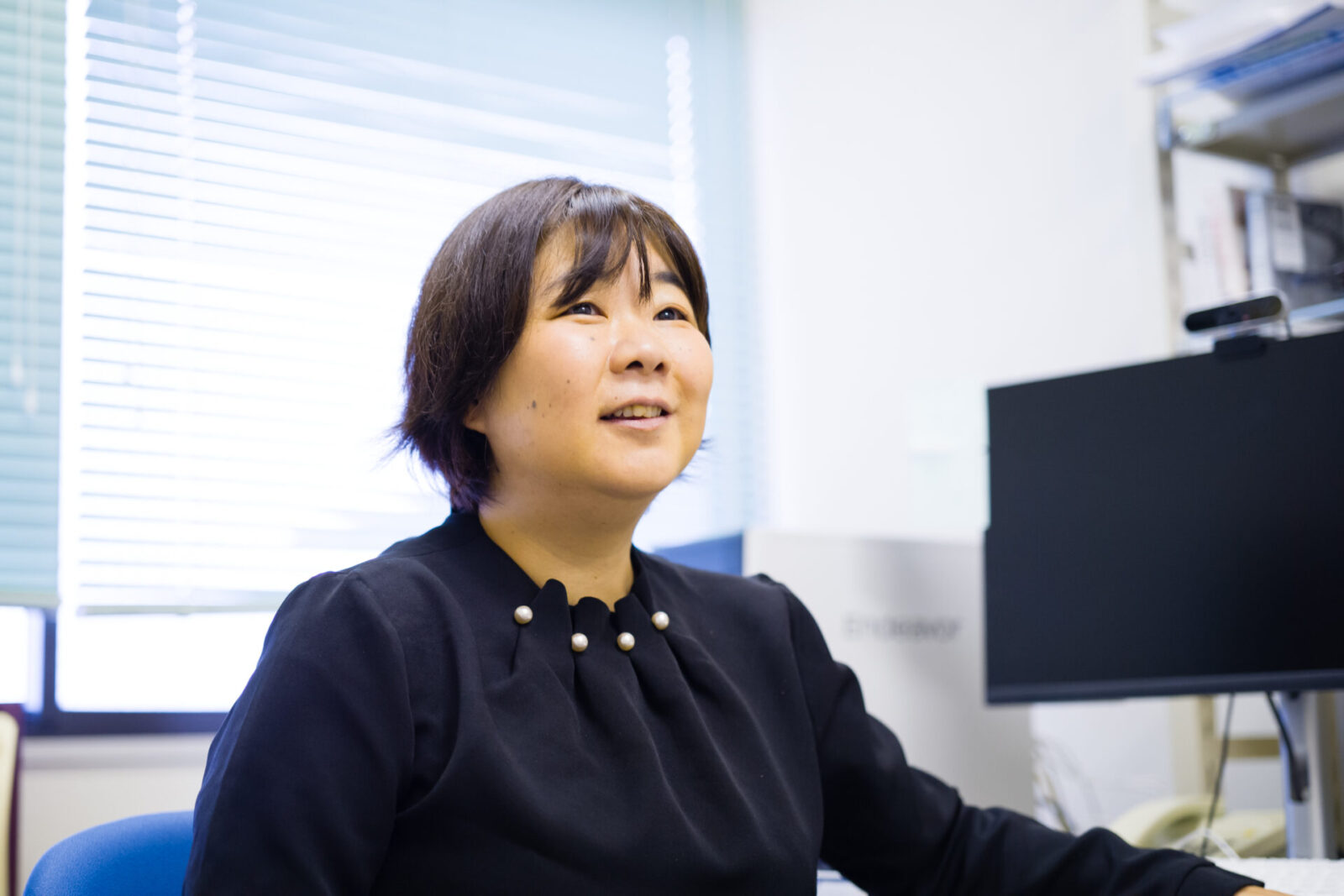
借りたものは、すぐに返さない。「貨幣の交換」と「贈与」の違いとは
——1杯10円のコーヒーや回しタバコなど、嗜好品を介した「気軽な贈与」によるフラットな人間関係について前編でお聞きしました。そもそも、タンザニアと日本で贈与のとらえ方に違いを感じますか?
全然違いますね。日本の人たちは、贈り物を受け取ると、すぐにお返ししようとするじゃないですか。それも、もらったものとなるべく等価のものを、すぐに返そうとする。
でも、考えてみてください。等価のものがすぐに戻ってくるなら、限りなく市場交換に近いと思うんですよ。パンを渡したら、等価のお金が返ってくる。
それなら、パンを売っているのと一緒ですよね?
もちろん等価のものを返す、日本の贈与のやりとりに意味がないわけではないんです。たとえば友達同士で同額のものを贈り合うことがありますよね。「だったら最初から自分で好きなものを買ったほうがいいんじゃない?」と思うかもしれないですけど、それは違うんです。
なぜなら、あの贈与は「私たち、対等な関係だよね」というのを確認する儀式なんです。
1000円のプレゼントをした友達から、100万円の指輪が返ってきたらどう感じるか想像してみてください。違和感がありますよね。そして「どういう含意があるんだろう? 私に何か特別なことを期待しているのか?」「もしかして『自分のほうが金持ちだ』とマウンティングされているのかな?」などなど、モヤモヤしますよね。
3000円のプレゼントをしたら、3000円くらいのものが返ってきたほうが、関係性が対等という感じがして気持ちがいい。

でも、タンザニアの人たちは私たちとは違って、贈り物をもらっても平気で10年間とか、年単位で放置するんですよ。
タンザニアで暮らしていると、日本の感覚のように「早く返さないといけない」というのが不思議に思えてきます。タンザニアの人たちもいつかは返すんですけど、返す機会が来るまでは返さない。もしくは、相手が必要とするまでは返さなくていいと思っている節があります。
——贈与における時間軸が全く異なるようですね。その違いはどこからくるのでしょう?
なぜでしょうね……。日本の人たちは、自分の自立性を脅かすような負い目や借りを持っていたくないと思うところがありますよね。
自立的な人間観のようなものが強いがゆえに、贈り物を受け取ったらすぐに返そうとするのかもしれない。
あるいは、労働というよりむしろ「時間を売って暮らしている」と言ってもいいほど、いまや日本では時間がすごく重要な概念になっている。「だから返済を急ぐ」という説明の仕方もあるでしょう。

——たしかに、自立と時間は、日本ではすごく大事にされていますね。
でも贈与というものは、ちょっと借りを残しておくのが秘訣なんですよ。
そうでなければ関係性が続かないですから。贈与の起源を振り返っても、借りはすぐに返すものではなく、貸した人が必要としたときに返すものなんです。
『ブルシットジョブ』『負債論』などの著作で知られるアメリカの人類学者のデヴィッド・グレーバーが、貨幣のない社会の贈与についてこんな話をしていました。
貨幣のない社会というのは、「私がいらないもの」と「あなたがいらないもの」を交換する社会ではありません。「『あなたが欲しいと言っているもの』を私は気前よくあなたにあげる。その代わりに『私があなたのものを欲しい』と思ったときに、そのものをちょうだいね」。そういう約束のもとに回っているのが、貨幣のない社会なんです。
決してAとBとを交換しているわけではない。同時、即時である必要はないんですよ。

企業や銀行に頼らない、独自のセーフティネット
——私たちの感覚からすると、「長い間、借りをあえて返さない」というのは新鮮に聞こえますね。「すぐに返さない」のがタンザニアにおける贈与の特徴なのでしょうか。
借りを返さない側の話だけではありません。“贈与する側”の心構えも、日本とは違います。
タンザニアの人は、困っている人がいたら助けはするけれど、すぐに贈与したものを返してもらおうとはしません。
むしろ、積極的に多くの人に貸しをつくる。
つまり贈与をする相手を増やして放置している印象があります。自分の「分身」を増やしているようなイメージでしょうか。
——いろんな相手に贈与をして放置する? 分身が増える? どういう意味か、くわしく教えてください。
つまり、「自分にまだ借りを返していない人が周りにたくさんいる」という状態を作るんです。もはや誰にどれくらい貸しているかわからないし、借りた側もどれくらい借りたかはわからない。
でも借りた側は「困っていたとき、自分にいいことをしてくれた人」であることは覚えています。そういう人を周りにたくさん作っておいて、いつか自分が「本当に困ったとき」に助けてくれればそれでいいと思っているんです。
——なるほど。いろんな人に少しずつ恩を売っておくことが、タンザニアの人たちなりのリスクヘッジになっている。
そうです。だから彼らは、いろいろなものを簡単に贈与してしまうんですよ。
タンザニア人の多様な生計のありようは、日本のビジネスの感覚とは異なります。たとえば露天商としてある程度の成功を収めたとして、露天が商店になり、企業になり……と事業規模を拡大していくことはほとんどないんです。
そうではなく、同じサイズの露天をもう一つ出したり、冷蔵庫を買ってソーダ売りを始めたり、コピー機を買ってプリントアウトサービスを始めたりと、彼らは小さな規模での多様な商いを増やしていきます。
とはいえ、自分の体は一つですし時間も24時間しかありません。
だから、新たにソーダ売りやプリントアウトサービスを始めようと思えば、通常は「人を雇おう」と考えるじゃないですか。でも、彼らは人を雇いません。
雇わずに、取引するんですよ。
——どんな取引ですか?
例えば、商いを増やしたいときは、仕事のない若者に冷蔵庫をあげて、取り決めをするんです。
仮に1日の売り上げが平均1000円だとすると、「そのうち200円を俺に納めろ。残りはどれだけ稼ごうが君の取り分だ」と。そうやって毎日自分に200円返ってくる状態を作ったら、その冷蔵庫はやがてその若者のものになる。

——個人同士の取り決めなんですね。見ようによっては、若者の独立支援でもある。
「単に若者が、冷蔵庫を分割払いをしているだけ」という見方もできるのかもしれません。でもちょっと違います。
冷蔵庫をもらったその若者は、単に冷蔵庫をもらっただけではなくて、お金を稼げる仕事を与えられ、生き延びさせてもらったわけです。
だから元の持ち主に対しては「あの人は俺に生きるチャンスをくれた人」と考える。
タンザニアの人たちはそうやって自分の資本を転がす際、誰かを雇用し、あくまで自分の資本として運用するのではなく、むしろ「積極的に手放す」ことによって、自分の「分身」のような存在の人間を増やしていくんです。
——「贈与」を通じて、自分の「分身」のような存在を周囲に増やしていくことが、自分自身のセーフティーネット作りにもなっているんですね。
タクシー運転手も、その方法で自分で稼げるようになっていきます。
もし銀行からお金を借りて中古タクシーを買うのだとしたら、返済が滞れば、担保を取り上げられたり車を取り上げられたりしますよね。でもお金をもっている人が、仕事もお金もない人に「お前はタクシーの運転手をしろ。俺には毎日5千円届けろよ。あとは知らん」みたいな形をとれば、渡すお金が滞っても事情を話せば、担保や車を取り上げられることはありません。
長くタクシーの運転手を続けていれば、やがて「もう十分元を取ったし、車は君のものだ」という感じでお金をもっている人に言われて、晴れて独立したタクシー運転手になっていく。
一方、元の持ち主からするとそのタクシーは自分が与えたものだから、彼が自分で稼げるようになったあとも、本当にタクシーが必要なときには一本電話をかければいい。そうすると例のタクシーがピューッとやってきて、自由に乗せてもらえる。そういう安心感があるんです。
「お金」より「人」を信用する理由
——タンザニアの人たちの態度は「計画的に考えて未来のためにいまを積み重ねる」というよりは、「いまこの瞬間、この関係」を大事にしている。むしろ、いまの関係を積み重ねた先に未来があると考えているように映ります。
それは確かにそうです。時間が未来に向かってまっすぐ進んでいるという感覚は、タンザニアの人たちにはほぼないです。なぜって、一貫したものが永続していくことが難しいから。一事が万事そうなんですよ。
タンザニアでは、14歳以上の銀行口座保有率がいまも20%程度にとどまっています。電子マネーの口座はあるけれど、そこにもたいした額は入っていない。
それは単に貧乏というだけではなくて、稼いだものを誰かのための別の事業に投資したり、あるいは支援するために人にあげてしまうから。彼らはそうやって「人間のかたちで貯金している」ようなものなんです。
——銀行より、人間の方が信用できるということですか?
ある日突然、銀行が潰れたら。紙幣が突然、紙屑になったら…….。
タンザニアにはそういう危機が割と現実的なものとしてあるんです。ドイツ、のちにイギリスの植民地になり、独立後は社会主義体制に、1980年代半ばに資本主義へと、社会システムがガラッと変わった歴史をもちます。
タンザニアの人たちにとって、政府や銀行は無条件に信用できるものではないのです。
一方で、人間であれば、戦争になろうとAIによって仕事が奪われようと、生きている限りはなんらかのことをしてくれるわけです。
タンザニアの人たちの置かれた状況からすると、銀行に預けたり現金のままで持っておいたりするより、人間にかけておいた方がはるかに安心なんだと思います。

「本当に困ったとき」を笑えるか? タンザニアと日本の人間観の違い
——小川さんの著書、香港に住むタンザニア商人を活写した『チョンキンマンションのボスは知っている』には「信用するな」というキーワードが出てきます。
だが彼らは「信用するな」と言いながらも、偶然に出会った得体の知れない若者を気軽に部屋に泊める。「信用するな」と私に忠告する相手と食事をおごりあい、カネを貸しあい、時には別の次元で「彼/彼女は信用できるやつだ」とも「信じていたのに裏切られた」とも言う。
『チョンキンマンションのボスは知っている』P51より
タンザニアの人たちは基本的に人を信用していないのに、「いつか返ってくる」と考えられるのは、どういうわけなんでしょうか。

私たち日本人はなんとなく「人間というのは一貫していなければならないもの」と考えていますよね。でも、彼らの人間観は違います。
タンザニアの人たちからすると「人はすぐに豹変するもの」なんです。
腹が減ったら機嫌が悪くなるし、満たされていれば気前も良くなる。生きていれば晴れの日もあるし、雨の日もあるだろう、と。
だから、タンザニアの人たちは自分の贈与が100%返ってくるとは思っていないです。
相手の機嫌が悪かったら返ってこないかもしれないし、裏切って逃げるかもしれない。でも、自分の分身をたくさん作っておけば、その中にはそのとき機嫌の良い人だっているはずで。誰かしらからなにかは返ってくるだろうと考える。
——「人はすぐに豹変する」からこそ、分身をたくさん作っておくんですね。
人間観が日本とは違うな、と感じたことがあります。
タンザニアの人たちは追い詰められた人のことを躊躇なく笑うんです。借金で首が回らないとか、浮気現場に奥さん乱入とか。そこで土下座したり硬直したり見苦しい言い訳をしたりしている人のことを思いっきり笑うんです。
そりゃ面白いはずなんですよ、追い詰められた状況というのは、その人の全身全霊、叡智の結晶が現れる瞬間ですから。
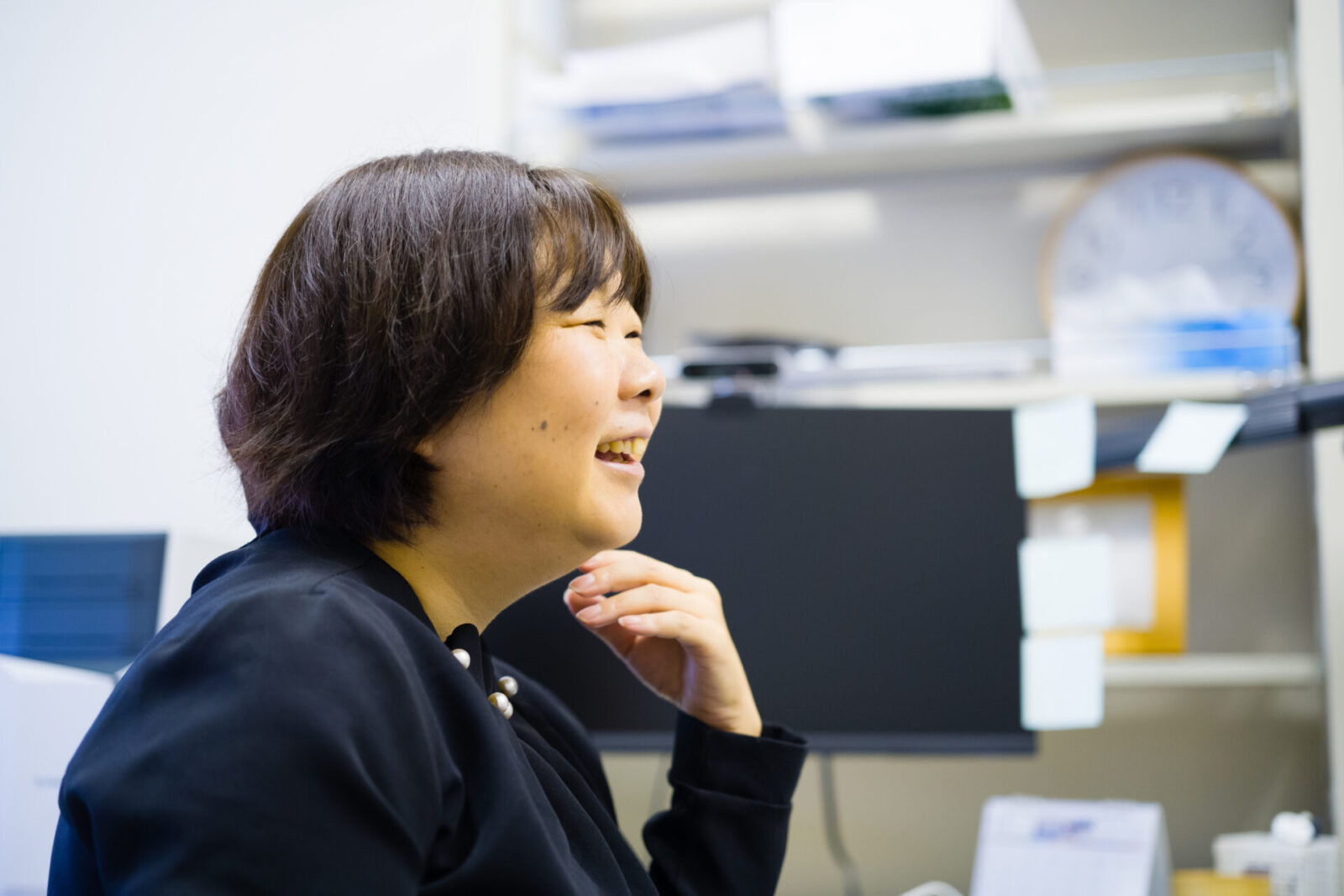
——誰かが本当に困ったときは、タンザニア人にとってはポジティブな笑いのネタになるんですか? 私たちの感覚だと、そんな状況の相手を笑うのは失礼にあたるような…..。
私たち日本人は、そういう追い詰められた人を笑うのはよくないと考えるじゃないですか。その違いはやっぱり、人間観の違いからくるんだと思います。
「一生懸命積み重ねた立派な社会的人格の裏側に、その人の本性がある」というのが私たち日本人の人間観でしょう。窮地になって、自分をうまくコントロールできなくなったときに、その仮面は剥がれ、見てはいけない素顔が現れてしまう。そのことにお互いに恐怖しているから笑えないのだろう、と。
一方のタンザニアの人からすると、窮地で豹変するのは当然のこと。
「ここでは土下座」「こういうときは逆ギレ」と「うわっつら」を変えながら、なんとしてもその場を切り抜けていくことは、その人の生命力、知恵の発露だと考える。
本性と社会的人格は分けて考えるものではなく、人はその時々の状況に応じて都度変化していくものなのだという人間観に立てば、思い切り笑ったところでなんの問題もないわけです。

システムと贈与の両立、そして嗜好品の効能
——「贈与」で人と人が助け合うタンザニアの社会は、将来に閉塞感の漂う、一人ひとりの自立が求められるいまの日本の社会と比べて幸福感が感じられると思いますか?
それはどうでしょう。タンザニアの人たちからすると、日本のしっかりとしたシステムや政府があることはやっぱりうらやましいことです。
たとえば病気になったとき。「知り合いのなかから医者とかタクシーの運転手を探さなくてもいい。保険でほとんどカバーできるなんて、日本は楽だよね」と彼らは言う。
別にタンザニアの人たちは幸福だから今のやり方を選んでいるわけではないです。
もちろん私たちからすると、そんな彼らの社会を「いいな」と思うことはいっぱいあります。私自身も「将来本当に困ったときに、孤独だったらどうしよう」と思う日もあります。そういう意味での孤独感は彼らにはないものかもしれないです。
でも、同時に「気軽な贈与」で成り立つ人間関係が鬱陶しくもあるわけですよ。
自分も助けてもらっているけれど、人からも「助けてほしい」と言われるわけだから。「……あの人、またお金を借りに来たよ」と思うことも当然ある。

——たしかに面倒くさいですね……。でも、部分的には参考になることもありますか?
その通りです。資本主義のシステムや近代福祉国家の制度に代替するものを作るというよりは、いろいろなシステムを作っておいたほうが、人間としてのレジリエンス(しなやかさ)は高まると思うんです。
贈与の世界だけですべてが回るかといえば、そんなことはない。
高額な難病医療なんて、彼らの力をすべて結集しても無理ですから。そういうちゃんとしたシステムはシステムとして維持、拡充されるべきです。
でも、「制度があるから贈与はいらない」ということではないですよね。ひとつの方法がどれほど優れていても、他の方法には別のよさがあります。
たとえば買い物においても「Amazonがあるから、リアル店舗はもう必要ない」ということにはならない。「リアル店舗で店員と会話しながらの買い物は楽しいし、クリックひとつで家にものが届くAmazonは便利」という選択肢の多さがいいはずです。
そういう意味では、私たちも小さな贈与を気軽に始めてみてはどうでしょう?むしろ嫌いな人に対してこそ、積極的に贈与したほうがいいと思います。
——小さな贈与なら始めやすいですね。でも、あえて嫌いな人に贈与するのはなぜですか?
贈与というのは、必ずしも大切な人にプレゼントを贈るといったような、既存の人間関係を強固にするだけのものではありません。
「見知らぬ人や敵意がある人を自分の側に取り込む」というのも贈与の機能の一つです。
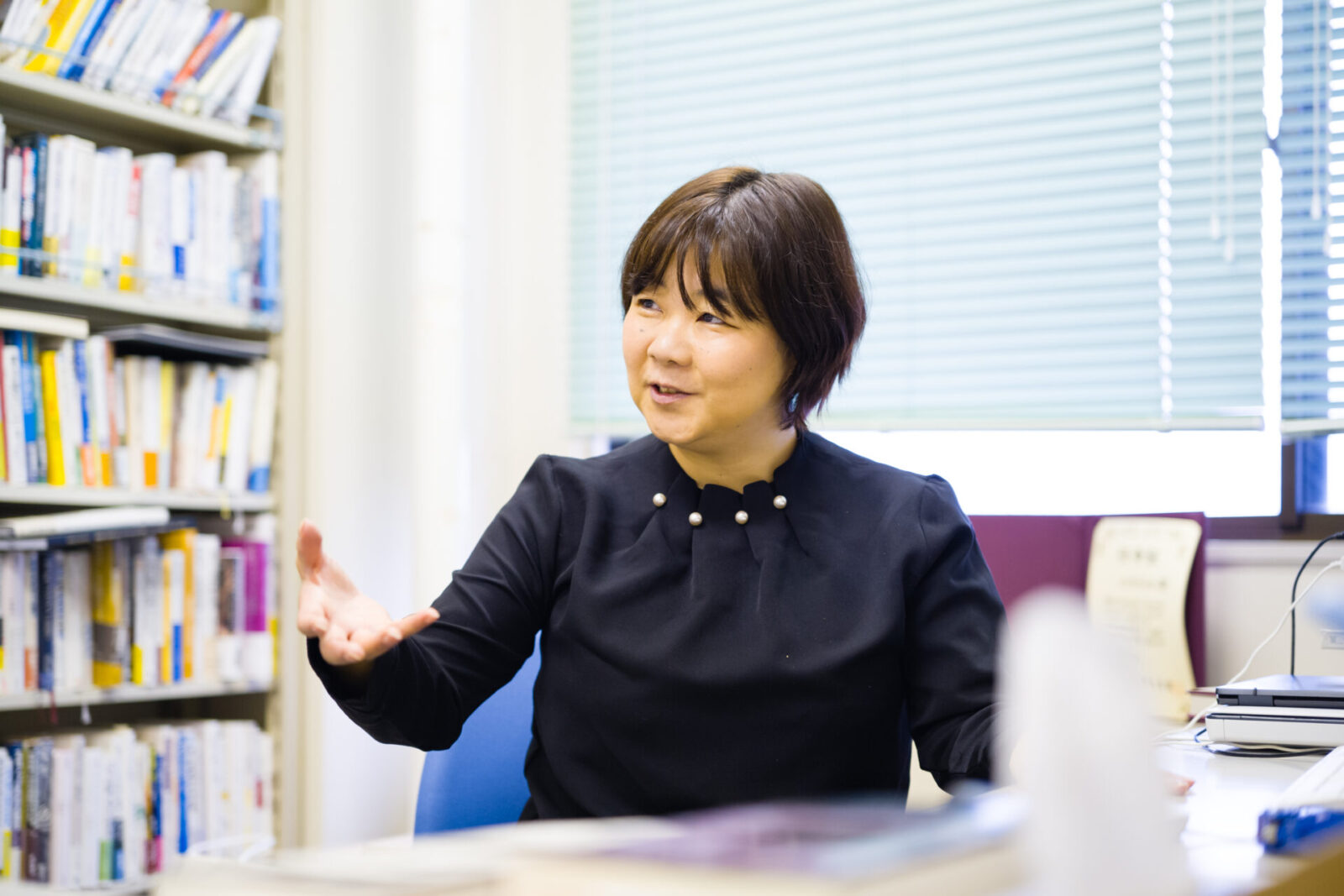
——なるほど、贈与を使って人間関係を変えていくんですね。
私は基本的に、人間はそんなにわかり合えなくていいと思っているんです。
大きな戦争といった諍(いさか)いを起こさずに、「いろんな人がいるね」と共存さえしていければいい。
全部を吸収して包摂して、わかりあう必要なんてないのではないでしょうか。とりあえず共存していけるような関係を担保するために、ときどき贈与するのはありです。
——贈与は、いろんな人が共存するためのツールになりえると。
そもそも日本社会から贈与が減っているかといえば、そんなことはないんですよ。ご褒美チョコのような自己贈与とか親しい友人、恋人などへの贈与はむしろ増えている。環境への贈与、公的贈与、ボランティアなどもそこまで減少していません。
なくなっているのは、それまで嫌々やっていた義務的贈与だけ。いわゆるお歳暮とかお中元とか、そういう類の贈与は減少傾向にあります。
でもその義務的贈与も、嫌々ながらもやっていたのには意味があるんです。そういう文化がなかったら、近隣住民との縁はあっという間に切れてしまう人がいるのです。
しょうがなくでも贈与をすること、なにかものを渡すことで、災害が起こったときや、自分が独居老人になったときに、ご近所さんが見にきてくれる確率は絶対に上がるはずです。もちろん鬱陶しさは切り離せないとは思いますけどね。
——面倒な風習でも、長期的に考えれば何かあったときの安心につながっていた。そう思うと、日本の義務的贈与もタンザニアの贈与に通じるものがあります。
今、日本で生きにくさや息苦しさを感じている人にとっては、いろいろなオプションを持っておくために、タンザニアの人たちの価値観から学べることもあると思います。
無理なく気軽にできるように、義務的贈与をもうちょっと楽しい贈与に変えられたらいいですよね。それこそITを活用するなど、今の時代に合った贈与のやり方はいろいろあるはずです。贈り物が必ず高級品の詰め合わせである必要なんて、ないんですから。
そういった意味では、気軽な贈与に嗜好品は最適ですよね。
コーヒーを奢るだけではなく、奢られたときは気持ちよく受け取る。そうして、性別や年齢、職業、貴賤の違いを超えた、フラットな人間関係をつくっていく。そんな贈与の世界もあったらいいですよね。

Editor / Writer。横浜出身、京都在住のフリー編集者。フリーマガジン『ハンケイ500m』『おっちゃんとおばちゃん』副編集長。「大人のインターンシップ」や食関係の情報発信など、キャリア教育、食に関心が高い。趣味は紙切り。
『DIG THE TEA』メディアディレクター。編集者、ことばで未来をつくるひと。元ハフポスト日本版副編集長。本づくりから、海外ニュースメディアの記者まで。企業やプロジェクトのコミュニケーション支援も。岐阜生まれ、猫好き。
