嗜好品には、体をつくる栄養があるわけではない。
生命維持に必要不可欠ではないのにもかかわらず、全世界で嗜好品はたしなまれている。
嗜好品は、人間らしく生きるために、なくてはならないものなのかもしれない。
嗜好品や嗜好体験を考えることは、人間が生きるためには何が必要か、ひいては「人間という生き物とは何か」に迫ることでもある。
現代における私たちの嗜好品や嗜好体験を探究するために、文化人類学や歴史学者などさまざまな一線の研究者に話を聞く、連載「生きることと嗜好」。
今回は京都精華大学教授の斎藤光さんの研究室を訪ねた。
前編「「場」が生み出す、人間らしい嗜好体験。幻のカフェーから浮かび上がるもの:科学社会学研究者・斎藤光」では、その瞬間で消えゆく、嗜好品や嗜好体験を研究する難しさとおもしろさについて教えてくれた斎藤さん。
これからの嗜好品を考える上で重要となるのが、将来のテクノロジーが「私たちの身体にどこまで介入するか」だと語った。
未来の嗜好体験を、斎藤さんと共に考えてみる。
(取材・文:吉川慧 写真:木村有希 編集協力:笹川ねこ 編集:呉玲奈)

香水とピアスから考える「嗜好」
──斎藤さんは以前、男性の香水に関する論考を発表されていましたね。こういった研究に興味を持ったきっかけは?
「嗜好品文化研究会」という研究会(現在は休止)で、香水にまつわる研究を報告しました。いろいろな分野の研究者が専門分野と嗜好品の関わりについて、事例やアイデアを発表する研究会でした。
日本では、80年代末に若い男性の香水がブームになり、90年代の終わりには、主に異性に対するイメージ戦略として、高校生から20代の男性に一定程度は香水をつけることが定着していました。
香水は、人間の身体性に関わるところがあります。ジェンダーによっても、香水をつける率は異なりますし、評価も違っていると感じます。
また、香水と同様に男性のピアスが受容されていく過程にも興味がありました。

──ピアスですか。
今ではピアスをつける男性は増えていますが、20〜30年前はそれほどいなかった。街中でも、ピアスをつけている男性を見かける機会はあまりなかったと思います。
1990年代に、私が授業を担当していた女子大の学生にピアスについてアンケートを募ったことがありました。「男性と女性、それぞれピアスをつけることについてどう思うか」と。
結果を見ると、女性がつけることは「本人が良ければ良いのではないか」という意見が大多数でした。
ところが、男性のピアスについては「似合うのならいいけど、似合わなかったらつけないでほしい」と厳しい意見が多かった。
当時のアンケートでは、女性からは男性のピアスに対して厳しい意見があり、それは女性のピアスに対する評価とは異なっていたんですね。
香水やピアス。そういった「嗜好品」こそ、異性への評価なり、ジェンダー観なりを切り取ることができる研究対象だと、あらためて発見しました。

スマホもまた、「嗜好品」なのか?
──過去から今へ。嗜好品のありようはどう変化しているのでしょうか?
嗜好品の在り方が拡張されてきたことは確かだと思います。
たとえば武庫川女子大の藤本憲一さんは、嗜好品を「アンチストレッサー」と定義しています。
つまり、緊張感を強いるようなものから一時的に逃避するような、「気分転換のためのお気に入りの品は、すべて嗜好品。例えば、スマートフォンも嗜好品の一つだと言えるでしょう」と。藤本さんの定義は、おもしろいと思います。

ただ、ここで僕が指摘したいポイントは、スマートフォンでの体験は、基本的には「間接的」であるということです。
──「間接的」な体験ですか。
例えば、Instagramにラーメンの写真が投稿されたとしましょう。私たちは誰かが投稿した写真をスマホで眺めて、楽しんだりする。
単純化すれば、スマホでおいしそうな食べ物の写真を楽しむことは、本を読んだり、記号や象徴を見て、私たちが内面的に考えてたりすることと同じです。
たしかに、嗜好品を楽しんでいるとも言えますが、「写真を見るだけ」と「実際に食べる」では、やはり体験のレベルは違います。
嗜好体験の原型は、どちらかと言えば、やはり「実際に食べる」ことではないかと思うのです。
つまり、「人間の身体が嗜好品や嗜好体験と密接に関係しているのではないか」というのが僕の見立てです。

テクノロジーや情報伝達の技術が時代とともに発展していますが、それに伴って実は身体性を伴うような「直接的」に経験できる領域が狭まってきているのではないかとも思います。
時間的にも、可処分時間が「間接的」なものに費やされる場面が増えている。
たしかに「飯テロ画像」を見て満足することもありますし、画像で満足できるのは「お金がかからなくていい」という考え方もあるとは思うのですけれど。
嗜好品の歴史を考えると、身体性と切り離せないものも多いと思います。

身体から離れた嗜好体験は生まれるのか
──これから先の未来、私たちを取り巻く嗜好体験はどのように変わっていくと思いますか。
個人的には、テクノロジーがどこまで人間の身体に介入するかがポイントだと思います。そういう意味で、漫画家・士郎正宗さんが描いた『攻殻機動隊』は非常に考えさせられる作品です。
『攻殻機動隊』では、脳からインターネットに接続できる電脳をもった人間や、義手・義足にロボット技術を付加したサイボーグ(義体化)となった人間、生身の人間、アンドロイドが混在する社会が描かれています。そういったテーマは、他のSF作品でもよく描かれていますよね。
ドラッグでいえば、快感を感じる物質を注射器でピュッと脳に注入すれば、ものすごい嗜好体験が得られるようになるのかもしれない。あるいはそういった物質すらいらなくなって、脳に機器をかぶせたら、電気刺激だけで嗜好体験が得られる未来が来るかもしれない。
いま嗜好品で体験しているものを、ゆくゆくは元来私たちが持っている身体から離れた人工的な回路で経験できるようになるかもしれません。
ただ、もしも実現できたとして、それが本当によい嗜好品なのか、あるいは嗜好体験なのかは考えないといけません。
僕自身は、身体を離れた嗜好体験に違和感があります。

──どんなところに違和感がありますか?
例えば、前述した脳だけで体験するドラッグには懐疑的です。
「身体で直接的に食べたり飲んだりする嗜好体験ではない回路をつくってしまって、人間として大丈夫なのか?」と問いたいですね。
「もともとある人間の身体」での嗜好体験が重要だと思っています。「等身大」の嗜好体験とでもいいましょうか。

──「等身大」の嗜好体験ですか。
とは言ったものの、「もともとある人間の身体」というのは何を指すのか、これを定義するのも、実は大変に難しい問題です。
「私たちの身体は、一体どういうものなのか」という身体論にも関わってきます。このあたりは、例えば薬と嗜好品の関係についてなど、いろんな話に広がっていき得るので、ひとつ「動物」という切り口から考えてみましょう。
科学的にいえばペットの犬、猫もすべて物質なので「モノ」になってしまう。でも、僕たちの社会では犬や猫を「モノ」と考えることには抵抗がありますよね。ペットの犬や猫は家族の一員ですし、法律でも命があるものとされています。
身体論をどうとらえるか? この論議は、時代によって人間の感受性が変わっていることも無視できません。動物論と身体論は別の話ではあるけれど、関連がないわけではない。

──動物論と身体論、どんな関連があるのでしょう。
具体的にいえば、動物に対する人間の感受性はすごく変化しています。1970年代の半ばにピーター・シンガーが『動物の解放』という本を上梓しているのですが、そこから動物を巡る議論が広がりました。
例えば動物実験。あるいは生物の授業で行われていた「カエルの解剖」について。2020年代の今は「動物福祉(アニマル・ウェルフェア)」が問題提起されるようになりましたね。
これは「動物の身体性をどうとらえるか」に加えて、「人間の感受性の変化」の現れだと、僕は考えています。
人間の身体と動物のとらえかたというとまったく別の話に見えるかもしれないけれど、身体性や感受性という点でお互いに影響を受けているのです。

嗜好体験が「文化」になる条件
──斎藤先生のテーマのひとつである「身体性」は、その時代や人々の意識を表してもいるんですね。
そうですね。もともとある身体の定義についてはさておき、話を戻すと身体性と嗜好体験はやっぱり切り離せないと思っています。
例えば、茶道では茶室に入る際には「にじり口」から入りますよね。狭くなった入り口に、正座をして膝を曲げて頭を入れるようにして、膝を押し付けるようにして茶室に入っていく。そのあとに床の間が目に飛び込んできたり、お湯の煮え立つ音が聞こえてきたりするように、茶室は設定されている。
このように、身体性に特化した嗜好体験や嗜好品には、「作法」が備わっています。
身体性がある嗜好品や嗜好体験に「作法」が加わると、「文化」と呼ばれて長く続くものに発展していくのではないでしょうか。
これが、未来に続く嗜好品のヒントなのではないかな、と思っています。

サウナの流行は、「等身大」の嗜好体験だからこそ
──「作法」や「文化」という視点で、斎藤先生が注目している嗜好体験はありますか?
最近のサウナブームも、実は嗜好体験の一つではないかと考えています。最近、僕自身もサウナに行くようになり、「ととのう」という概念がわかるようになりました。
コロナ禍を経て、京都の銭湯には若い人がかなり来るようになりました。京都精華大学の学生たちとも、たまにサウナの話をすることがあります。
サウナで「ととのう」を求めるのは、身体へのある種の嗜好体験なのではないでしょうか。

入る時にはちゃんと水分を摂って、一定時間をサウナで過ごし、汗を流し、水風呂に入る。サウナにも一定の「作法」があります。
嗜好品というのは「体験」です。その「体験」を作るためには、作法や設定が込められていないと深まらないような気がします。
──「作法」や「設定」は、同じ嗜好を嗜む人同士の「共通言語」とも言えそうです。
サウナにしても、「何分間入るか」「どう入るか」は人それぞれですよね。そこに多様性があることも広がりがあっておもしろいと思います。
最初は友だちと一緒にサウナに行っていた学生も、いまは自分なりの楽しみ方というか「作法」があるようで、一人で行くと言っていました。
ただ、「この作法しか認めない」といった原理主義に陥ると、入り口や道が狭まってしまい、サウナという文化は廃れてしまうかもしれません。
作法も設定も柔軟で多様であること。それらが自分の体験と一体になること。それが嗜好体験の一番よい状態かもしれない。
これまでも、そしてこれからも、それぞれが「等身大」で楽しめることが嗜好体験において大切なことだと思います。
流行の濃淡はあるにせよ、人間が嗜好品や嗜好体験を手放すことはない。これからも時代を表す嗜好品という切り口から「人間」に迫っていきたいですね。
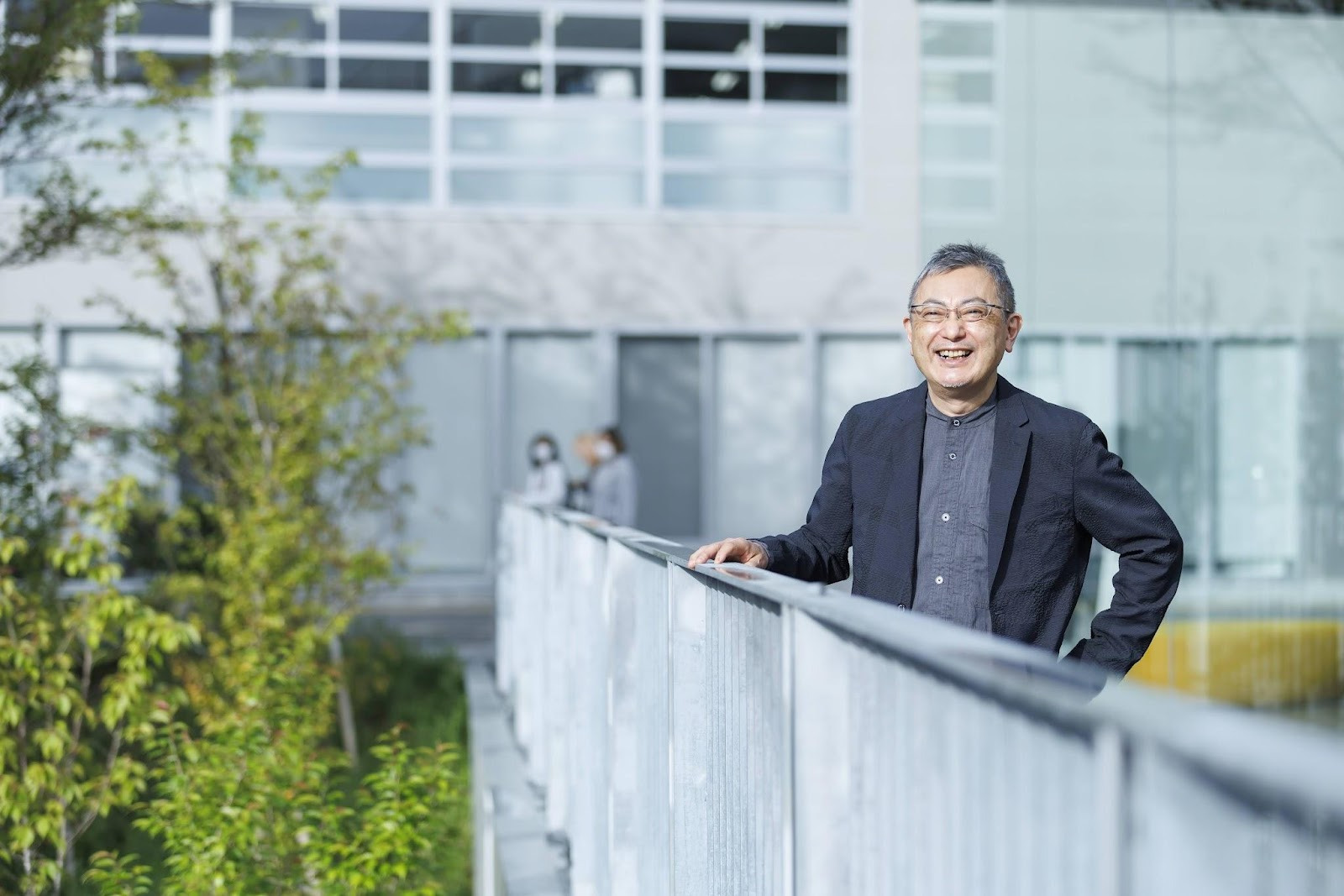
Business Insider Japan記者。東京都新宿区生まれ。高校教員(世界史)やハフポスト日本版、BuzzFeed Japanなどを経て現職。関心領域は経済、歴史、カルチャー。VTuberから落語まで幅広く取材。古今東西の食文化にも興味。
Editor / Writer。横浜出身、京都在住のフリー編集者。フリーマガジン『ハンケイ500m』『おっちゃんとおばちゃん』副編集長。「大人のインターンシップ」や食関係の情報発信など、キャリア教育、食に関心が高い。趣味は紙切り。
『DIG THE TEA』メディアディレクター。編集者、ことばで未来をつくるひと。元ハフポスト日本版副編集長。本づくりから、海外ニュースメディアの記者まで。企業やプロジェクトのコミュニケーション支援も。岐阜生まれ、猫好き。
