「土」を知れば、嗜好品や嗜好体験の今と未来が見えてくる——。
コーヒー、お茶、たばこ、ワイン、ビール……こうした代表的な嗜好品にはある共通点がある。
それは、いずれも植物が原料であることだ。元をたどれば「土」に行き着く。そこからさまざまな加工プロセスを経て、私たちに豊かな時間をもたらしてくれている。
嗜好品を語るとき、「土」は欠かせない要素なのである。
だが、とても身近な存在である土のことを、私たちはほとんど理解していないのではないだろうか。
たとえば「土とは何か」というとてもシンプルな質問にさえ、明確に答えられる人は少ないはずだ。ましてや、「どのような土で植物はよく育つのか」という問いに何らかの答えを提示できる人はかなり限られるだろう。
そんな「土」をめぐる疑問を解き明かすため、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所で主任研究員を務める、土壌学者の藤井一至さんにインタビューした。
お茶やお酒、あるいは果物は、どのような土に根付き、いかにして育まれ、私たちの元に届いているのか。
(文:鷲尾諒太郎 写真:田野英知 編集:小池真幸)
旨みのあるお茶は「酸性の土」が育てる
——今回の「DIG THE TEA」のインタビューでは、土と嗜好品の関係について質問していきたいのですが、そもそも「土」とは何なのでしょうか?
「どこからどこまでが土か」という問いは非常に難しいんですよね。
土とそうでないものを分かつのは、生物活動の有無です。
たとえば腐葉土は土ですね。でも、葉っぱが木についている時点では、土ではない。また、葉っぱが地面に落ちた瞬間もまだ土ではない。
地面に落ちて微生物が分解し始めた瞬間から土になります。植物だけでなく、動物にもあてはまります。

——土とは、「微生物によって動植物の遺体が分解されたもの」であると。
いえ、それだけなら納豆だって土になってしまいます。
土は、「生物」ゾーンと「岩石」ゾーンが重なり合う場所で生まれます。生物だけでも、岩石だけでも土ではありません。「岩石」と「土」を峻別する際も、生物活動の有無で分けます。
つまり、生物活動がまったくない層は「岩石」ゾーンであり、岩石と共に生物活動が観測できればそこは土ゾーンだということになります。
ただし、深い地層でも生物活動が見られることがあります。そこで便宜的に、植物の根や微生物活動によって岩石が変質している深さまでを土として扱っています。
「土」と「土ではないもの」を定義することすら、簡単なことではありません。
——定義が難しいとはいえ、お茶やコーヒーといった嗜好品の原料となるさまざまな植物は土から栄養を吸収しながら育っている、ということは事実なのではないかと思います。嗜好品にとって、土とはどのような存在なのでしょうか。
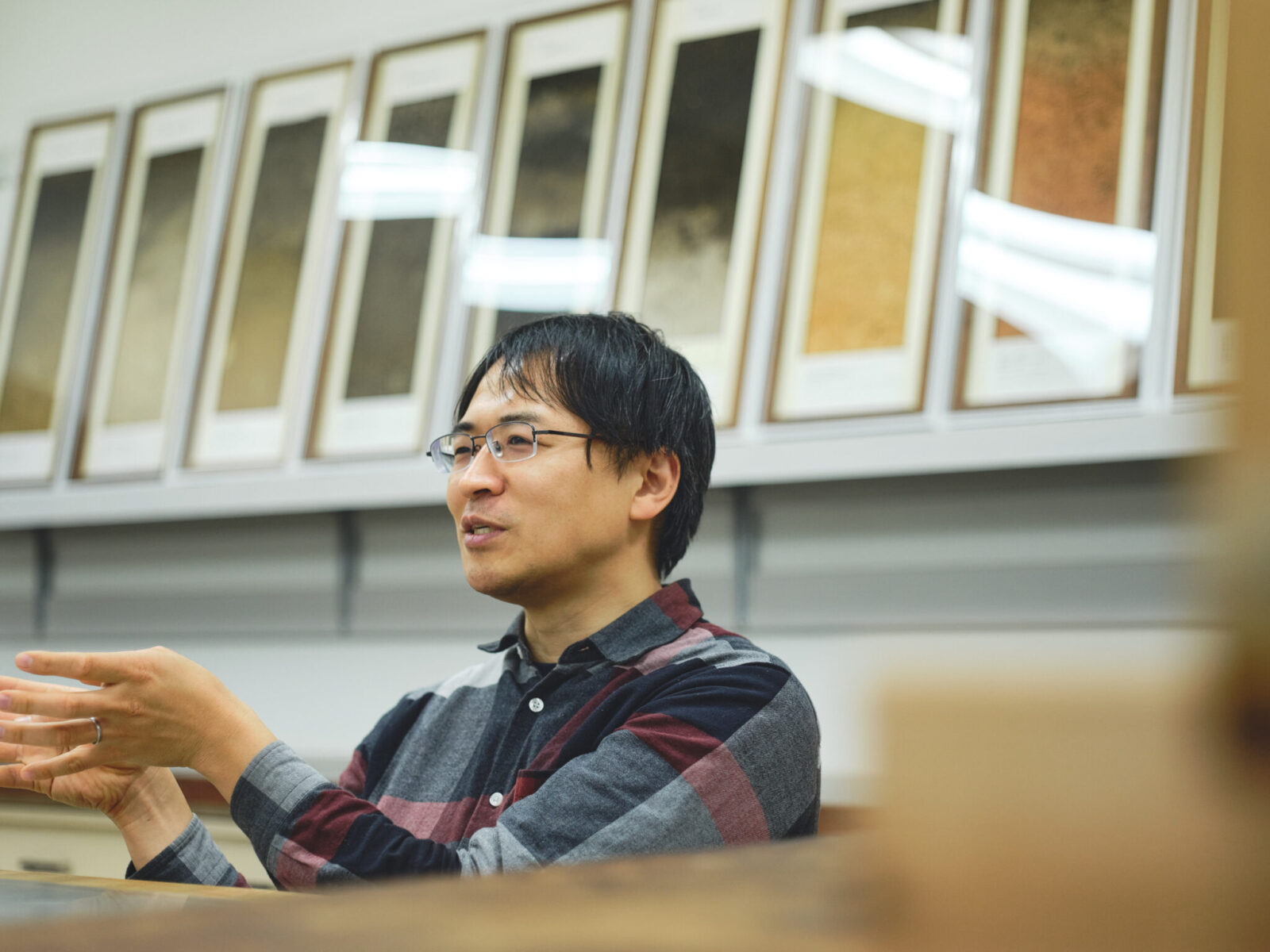
個別の嗜好品と土の関係を見ていきましょう。『DIG THE TEA』というメディアですから、まずはお茶がいいですかね(笑)。
お茶のうまみ成分の一つに、テアニンというアミノ酸の一種があります。一般的に旨味があって美味しいとされるお茶には、このテアニンが多く含まれることがわかっていますが、テアニンを緑茶の原料となるチャノキにたくさん送り込むためには、簡単に言えば、土にたくさんの窒素肥料を入れなければなりません。
お米や野菜などの畑でしたら、1ヘクタールあたり窒素ベースで60~100kgの窒素肥料を入れます。一方、高級なお茶をつくる畑に入れる窒素の量は、1ヘクタールあたり600〜1000kgにもなる。
——うまみ成分のテアニンがたくさん含まれた茶葉を収穫するには、多くの窒素肥料が必要になるのですね。
ただ、チャノキはすべての窒素を吸い上げ、テアニンを生み出すわけではありません。
窒素肥料を多く入れても、チャノキが吸収できるのは15%程度です。
すると、土に窒素が余ってしまう。余った窒素の一部は硝酸に変化します。結果的に土がかなり酸性になります。
たとえば、静岡県の土は、自然状態であればpH4.5~5.5くらいですが、窒素肥料を大量に投入すると、それが3.5くらいにまで下がります。
あまりピンと来ないかもしれませんが、pHが1下がるということは水素イオン濃度が10倍に増えるということで、そうなると土からアルミニウムが溶け出してきて、作物の多くは枯れてしまいます。
ですが、チャノキはむしろ酸性の土が大好きなので、元気に育つんですよね。

環境保全と品質のバランス、という難題
——美味しいお茶を育てるためには、土を酸性に保つほうがいい、ということでしょうか。
そうなのですが、程度にもよります。土が酸性になりすぎ、その水が川に流れ込むと、魚が死んでしまうんです。かつて静岡でも問題になりました。
それに、窒素は二酸化炭素の約300倍もの温室効果があると言われている亜酸化窒素ガスを排出してしまうのです。つまり、無駄に窒素を撒くと、地球温暖化を加速させてしまうリスクもあります。
そういった背景から、現在お茶農家の多くは窒素肥料の削減に努めています。
——具体的にはどのような方法でしょうか。
一つは有機肥料への切り替えです。化学肥料よりも雨で流出しにくいのが魅力です。ただし、2021年、スリランカ政府は国内で使用するすべての肥料を有機肥料にする方針を打ち出しましたが、この取り組みは国内に大混乱を招き、失敗に終わりました。
土壌に生息する微生物が有機肥料を分解することによって窒素が生み出されますが、人間は微生物の分解速度を調整することはできません。だから、有機肥料だけに頼ると、適切な時期に適切な品質のお茶を生産できなくなってしまうリスクがあります。また、有機肥料は重いので、労働力不足が深刻な国内では容易ではありません。
お茶の品質をコントロールするためには、ある程度は化学肥料に頼らなければなりません。そこで、点滴潅漑などでチャノキが必要とする時期に効果的に肥料を供給する技術も普及しています。
環境保全と嗜好品としての品質のバランスをどう保つか。美味しいお茶を飲めている背景には研究開発者やお茶農家の方々の尽力があるわけです。

ワインと土壌の関係性──「肥沃であればいい」わけではない
——藤井さんは、ワインのテロワール(ブドウ畑を取り巻く土壌・立地・気候といった自然環境要因)に関する調査もされていますよね。やはり、ワインの原料となるブドウも土との関係が深いのでしょうか。
僕はフランスのボルドーでワインと土の関係を調べた経験があり、そこでは主にメルローとカベルネソーヴィニヨンという品種のブドウが育てられていました。
メルローは早熟な品種で、ゆっくり育てないと、ただただ甘いだけのブドウができてしまう。それをワインに用いると味に深みが出ない、土壌温度の上昇しにくい保水性の高い粘土質の土壌でゆっくりと育てられます。
対してカベルネソーヴィニヨンは、元来ゆっくりと育つ品種。ですから、土壌温度の上昇しやすい砂地で育てても味に深みのあるブドウができる、という違いがあります。
——同じ「ワイン用のブドウ」でも、品種によって適した土壌が異なるわけですね。
はい。特に印象深かったのはマルゴーという地区の畑です。
マルゴーというエリアは、ボルドーの中でも特に品質が高いワインを生み出すことで有名ですが、土は肥沃ではありませんでした。石がたくさん混ざった砂利のような土壌だったんです。
マルゴーでつくられているような骨格のある高級ワインをつくるためには、とにかくブドウにストレスを与えなければいけません。だから、作物をつくる土づくりとは違うんです。
ワインの骨格の正体はポリフェノールです。栄養の多い土ではブドウは速く育ちますが、栄養の少ない土で育ったブドウは虫や乾燥などのストレスから自らを守るために、タンニンというポリフェノールの一種を多くため込むようになります。そして、このタンニンがワインの味に深みを与えるとされているんです。
だから、どっしりと重厚な味わいの赤ワインをつくるためには、むしろ即効性のある栄養分は土に入れない方がいい。
——「いいワイン」は必ずしも「肥沃な土壌」から生まれるわけではないのですね。
土とワインの関係でもう一つ興味深いのは、チリワインですね。
銘柄にもよると思うのですが、チリワインは「土の匂い」に特徴があるとされます。その匂いの元になっているのが、ゲオスミンという物質です。
雨が降った後の土っぽい匂い、土砂崩れ直前に発生するとされる土の臭い、魚や水の泥臭さ、それらはいずれもゲオスミンが原因物質だとされています。
ゲオスミンを生み出しているのは、土の中にいる放線菌という細菌なんです。放線菌はブドウの根、葉、果実に付着します。そして、その果実を発酵する中でゲオスミンがワインにほのかな香りをもたらすという話です。
これは一例にすぎませんが、土地土地の土壌、あるいはその中にいる微生物がワインの味わいや匂いの個性を生み出しているのです。
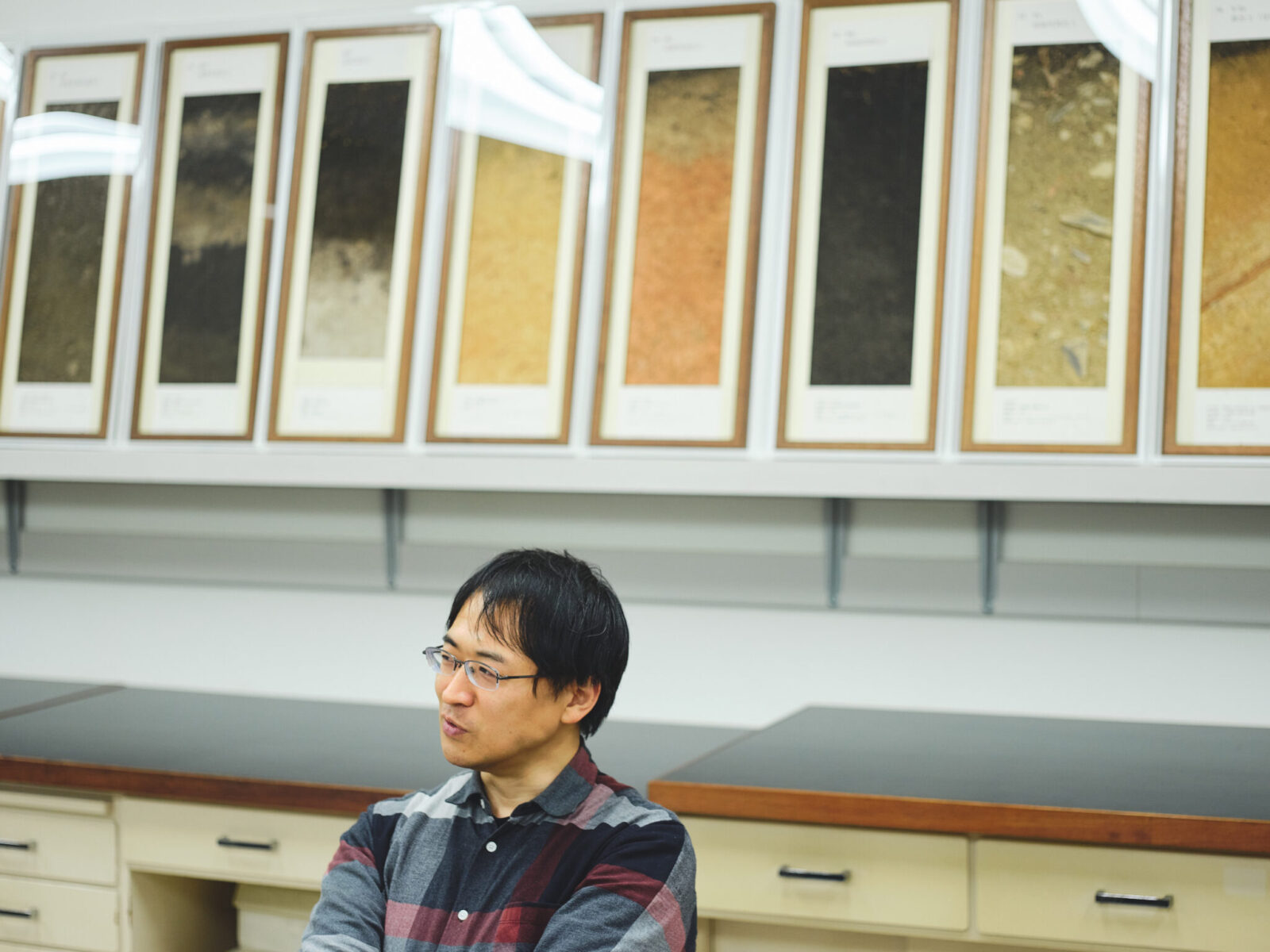
「土」は日本酒の味に影響を与えているか
——他のお酒にも同じことが言えるのでしょうか。たとえば、日本酒はイネという植物から生み出されていますが、ワインほど「土」に着目されているイメージがありません。
日本酒のつくり手の中にも、土に注目している方はいます。実際、以前ある酒蔵の会長さんが「土と日本酒の関係を教えてくれ」と僕のところにやってきたことがあります。ただし、土とお米、ひいては日本酒の味の関係は、とても難しいんです。
——ワインのようにはいかない?
当然、お米の味は日本酒の味を左右します。そこは確実につながっています。気候とお米の味の関係も有名です。昼夜の寒暖差の大きい中山間地でお米を育てると、お米はデンプンをため込むようになり、甘いお米になる。
しかし、土とお米の味の因果関係は、現時点ではわかっていないんです。
僕のところにやってきた会長さんは「同じ気候、同じ水と同じ醸造法で日本酒をつくっても、味が違う。違いは土なんじゃないか」と推論しました。
粘土鉱物や栄養成分、微量元素等を分析し、土が大きく違うことはわかりました。しかし、そこからお米の味、お酒の味にどうつながるのか、科学はまだそこを十分に説明できていないのです。
謎が多いところも土の魅力の一つです。

イチゴの「甘い香り」の理由
——嗜好品の原料となる作物と土の関係には、たくさんの謎が残っているわけですね。
はい。でも、お茶やお酒以外で言えば、果物、特にイチゴに与える土の影響は大きいことがわかっています。
——必ずしも「栄養を摂るため」に食べられているわけではないという意味では、フルーツも嗜好品の一つと考えられそうです。
イチゴにはフラネオールという匂い物質が含まれていて、この物質がイチゴの甘い香りの元になっていると言われています。
このフラネオールは、イチゴそのものが生み出しているわけではありません。
土の中にいるメチロバクテリウムという細菌が根や茎を伝って、葉に至り、葉の中にある物質をフラネオールにつくり変えるそうなんです。そうして、イチゴの実に運ばれる。
だから、熟したイチゴの採れたてが最高に風味がいい。我が家では家庭菜園をしているのですが、イチゴだけはスーパーに並んでいるものよりも、家で採れたものをすぐに食べるのが美味しい。

——え、イチゴだけですか?
家庭菜園をやってみてわかったのは「基本的に、野菜は買った方が美味しいし、コスパもいい」ということ(笑)。
トマトなんか、毎日欠かさず水やりをして、ようやく採れた2つがそこまでおいしくないこともある中、スーパーに行ったら5個で100円の美味しいトマトが買える。「これ、100円でいいの?」と思いながらいつも買っています。
でも、イチゴだけは自分でつくる価値を見出しています。
——では、イチゴは土の近くで採れたてを食べた方がいい?
香りも含めた質という観点から言えばそうかもしれませんが、土ってとても手強いものなんです。
イチゴ農家に限ったことではありませんが、年に一度は土を消毒しなければ、うまく作物が育たない植物が多くあります。特にイチゴはデリケートな植物なので、人間がうまく土をコントロールしなければなりません。
中には何年も消毒しなくてもイチゴが育つ土もあります。そういった土は「発病抑止土壌」と呼ばれていて、そこにはヒントがあるかもしれませんが、万能な処方箋は見つかっていないのです。
微生物と植物の「創発活動」が、あらゆる作物を生み出す
——さまざまな微生物の働きによってつくられているからこそ、土をコントロールするのは難しいのですね。
コーヒースプーン1杯分の土の中には、100億を超える細菌がおり、1マイクロメートルの菌糸が、数百メートル分張り巡らされているとされています。それに、一口に微生物といっても細菌や菌類(きのこやカビなど)、ウイルスなどがおり、土の中ではそれらが蠢(うごめ)き、栄養分を循環させているんです。
それらの微生物たちは、何も人間のために働いているわけではありません。
それぞれが自らが生存するために動く中で時に助け合い、時にぶつかりながら、共存しているわけです。そして、その結果として動植物を分解したり、栄養素を植物に送り込んだりする機能を果たしている。

——土の中にいる微生物たちは、嗜好品や野菜、果物を育てるために生きているわけではない。
一つ一つの微生物はトマトの設計図を持っていません。多様な微生物が、その他の微生物と協力、競争しながらトマトができているのです。畑によって年によって異なる微生物が働いていると思いますが、結果として毎年トマトが実るわけです。
イチゴだってそうです。イチゴの匂いの元であるフラネオールは、メチロバクテリウムという細菌とイチゴの相互作用によって生み出されているという話をしましたが、フラネオールだって「イチゴの匂いの一部」でしかありません。他にもさまざまな物質や微生物によって、イチゴの匂いは構成されているはずですが、私たちはまだその全体を把握できていません。
トマト一つ、イチゴ一つが多様な微生物、植物の織りなす創発現象の賜物なんです。
——私たちが口にするさまざまな野菜や果物は、ある意味では「偶然の産物」なのですね。
私たち人間もそうだと思います。たとえば、いま僕はインタビューを受け、あなたはインタビューをしているわけですが、それが社会にどんな影響をもたらすかなんて、誰にもわかりませんよね。
すべての人のすべての行為がそうだと思います。だけど、「どんな影響をもたらしているのかわからないから」とすべての人間が活動を止めたら、社会は崩壊します。
誰も世界の設計図なんて持っていません。
だけど、それぞれがそれぞれの役割を果たすことで世界は成り立っている。
そういった意味では、私たちもトマトやイチゴに栄養を届ける微生物と同じなのかもしれませんね。

日本のテロワールで育まれる嗜好品を
——土の中には、とても複雑で奥深い世界が広がっているのですね。日本で嗜好品づくりに関わる方々が、土に向き合うことで得られる示唆があるとすれば、それはどのようなものでしょうか。
これは嗜好品を生産している方々に限った話ではありませんが、日本のマーケットは人口減少に伴って小さくなっていくことは自明です。海外に目を向けるとなると、ブランディングが必要になります。
そのときに問われるのが、先ほども言及した「テロワール」だと思います。
僕自身、海外で食べておいしかったものを、日本に持って来てみたら全然おいしく感じなかったということがよくあります。「どこで」「何と(併せて)」食べるかによって、さまざまなものの味わいは大きく変化するんです。
日本で親しまれている嗜好品は、日本の土で育まれ、その中で味わうからこそ、おいしく感じられるのかもしれません。

——たしかにさまざまな名産品も、それらが育まれた土地で食べるとよりおいしく感じられる気がします。
そういったものが海を越えて受け入れられないのかと言えば、そんなことはありませんよね。むしろ、フランスのワインなどはその背後にあるテロワール自体がある種の物語として作用し、世界中で親しまれている。
日本でつくられるお茶やお酒などの嗜好品が、世界でどう戦っていくのかにとても興味がありますし、土を含めた日本のテロワールには大きな可能性があると思っています。
——日本のテロワールを生かした嗜好品づくりが求められていると。
テロワールは土に限った話ではありません。いかに地域の特性を組み込んだ物語を生み出すのか。歴史的に嗜好品は必ずしもエコなものばかりではありませんでしたが、今後は環境に配慮したものづくりという視点も欠かせません。
たとえば、インドネシアではアクイラリア(東大寺正倉院の蘭奢待が有名)という香木が盛んに生産され、主にアラブ諸国で嗜好品として人気を博しています。
お酒が禁止されているアラブ諸国では、嗜好品として香りを楽しみます。高級なものであれば、1キロあたり数百万円ほどの値が付くこともあるそうです。
香木は木ですので、生産を続けるためには木を植えなければならないわけですね。そうすると森が豊かになり、その下で土も再生します。嗜好品の生産が環境を守ることにもつながっているわけです。
これはあくまでも一例ですが、日本酒のテロワールのように、日本にもシーズはたくさんあります。日本ならではの土を活かした嗜好品が根付いていけばいいなと思っています。

》特集「嗜好を探求する」すべての記事はこちら
1990年、富山県生まれ。ライター/編集者 ←LocoPartners←リクルート。早稲田大学文化構想学部卒。『designing』『遅いインターネット』などで執筆。『q&d』編集パートナー。バスケとコーヒーが好きで、立ち飲み屋とスナックと与太話とクダを巻く人に目がありません。
編集、執筆など。PLANETS、designing、De-Silo、MIMIGURIをはじめ、各種媒体にて活動。
1995年、徳島県生まれ。幼少期より写真を撮り続け、広告代理店勤務を経てフリーランスとして独立。撮影の対象物に捉われず、多方面で活動しながら作品を制作している。
