お茶の時間のような、心が溶けるひとときを探究する「DIG THE TEA」。私たちは現代の「ポジティブな逃避の時間」をめぐる探究と冒険を続けている。
「ポジティブな逃避」とは、シンプルに突きつめれば、「休むこと」とも言い換えられる。
今回、『問いの立て方』(ちくま新書)などを上梓し、学問論をテーマに活動する京都大学の宮野公樹先生を訪ねた。学際融合教育研究推進センター准教授である宮野先生は、哲学的な対話によって、研究者がその研究者精神を研ぐような場をつくる活動を続けてきた人物だ。
現代の私たちにとって、休みとは何か。
ポジティブな逃避の時間とは、どんな時間なのか。
京都大学の古風な施設にて、宮野先生に休みや時間をめぐる問いを投げかけてみた。
人にとって「休み」とは何か? 草刈りの時間を考える
──早速ですが、宮野先生自身は「休み」というものをどう捉えていますか?
学問や研究には、いわゆる完全なる休みはありません。私たち研究者は四六時中、学問のことを考えています。アーティストの方々も、いつも創作について頭のどこかで考え続けている点では、きっと同じでしょう。タイムカードでオンとオフが区切られる仕事とは少し異なります。
──休みがない……。そんな日々が続くのはつらくないですか?
確かに、つらいのかもしれない。でも別の角度から見れば、研究者にとって仕事なんてなくて、全部休みなのかもしれない。
ではそんな僕たち研究者にとって、休みとは何か? 別のことに没頭することです。没頭とは、脳も身体もそのことに浸り切ることです。
たとえば僕が最近没頭できるのは、草刈りです。

──草刈り、ですか。
僕が住んでいるところの駐輪場近辺には、雑草が生える小さな空き地があるんです。
どんどん伸びる草を見ながら、委託している業者さんが草を刈るのを待っていたんですが、ある日、ご近所さんが自分の家の周辺を刈っているのを見て、ハッとしたんです。
「あ!業者さんが来るのを待たなくても、草は自分で刈れるんだ」という当たり前の事実に気づいたのです。そこからのめり込むのは早かったですね。すぐに自分の鎌を買いに行きました。
無心でザクザクと草を刈り続ける快感たるや!

草を刈る尖った音も、立ちのぼる草の匂いも、汗をかきながら肉体を動かす快感も、その後に地面がきれいになって日常空間が快適になるのも好き。いいことづくめですね。
非常によく研いだ鎌の刃を草に当てると、チン!という澄んだ音がする。日本刀もこんな音がするのかなと思いながら研ぎます。結局、4、5本の草刈り鎌を買い揃えました。
──まさに没頭ですね。
先日、「こんなに素晴らしい営みを独占していていいのか?」という思いから、洗剤のCMになぞらえて、「草刈り愛してる会」を一人で立ち上げ、マンションにポスターを貼ったほどです。
とはいえ、誰かと足並みを揃えるわけではなく、活動は一人で黙々と草刈りをしています。

草なんて、刈ってもまた生えてくるから、没頭する対象としてムダに思う人もいるかもしれない。それでも没頭する時間そのものが、僕にとっての休みです。
これは本業である研究からの脱却ではありますが、本業と休みは、同じ人間の営みとしてつながっているんです。
──研究も休みも、本来は人間としての営みの時間であると。
「生きることは魂の世話をすることだ」。これは、古代ギリシャの哲学者ソクラテスが残した言葉です。生きることは、自分の気持ちにちゃんと正直になっておくということなのだと理解しています。
自分の考えていることに敏感になって、直感を研ぎ澄ませていくのが大事です。僕にとっては、草刈りにも学問にも分け隔てはありません。自分の営みという点で、すべてに通じている。
「計測できる時間」と「計測できない時間」

──宮野先生にとっては、「没頭」する時間は、どのような時間でしょうか。
古今、時間に対していろんな哲学者が言葉を残しています。どこかで読みかじっただけなんですが、僕はフランスの哲学者アンリ・ベルクソン(1859-1941)の時間の捉えかたが好きです。
たしか、ベルクソンは時間には2種類あると言っています。時計によって1秒1分均等に計測できる時間と、そうではない質的な時間です。
──時計で測れる時間はわかりますが、質的な時間とはどういうものでしょう。
質的な時間とは何か。
たとえば、集中してあっというまに時間が過ぎ「もう夕方!?」と驚いたことはありませんか? 集中力が高まって感覚が研ぎ澄まされたとき、「ゾーンに入る」という言い方もありますね。逆に、子どもの頃は、たっぷり時間があるというか一日が流れるのが遅くて仕方なかった人もいるでしょう。
そういった、刻むことのできない空間的な要素を排除した時間が「質的な時間」であり、本来の時間である。質的な時間のほうが時間の本質だと、ベルクソンは言っています。
例えば、遊ぶように、心が溶けるこの時間を探究している「DIG THE TEA」の取り組みは、言い換えれば「時間とは何か」を哲学する挑戦だと、いえますよね。
「仕事」の対義語は「休み」なのか? 現代的な思考の癖とは

──私たちは、日々追われるように忙しく過ごす現代の人たちは、もっとポジティブな逃避の時間(ポジティブ・エスケープ)が必要ではないかと考えています。
最初の質問をお聞きして、違和感を感じたのは、「休み」と「仕事」を二項対立で捉えていたことです。そもそも「仕事」の反対にある概念は「休み」ではないでしょう。
では「仕事」の反対にあるのは何か?
よく言われるのが、仕事を「稼ぐこと」と捉えるなら、「消費」となります。休みになると買い物をする人は多いですね。
では「休み」の反対は何か? それは「存在」なのかもしれない。
「休憩」なら仕事の合間にとるものという感じですが、「しなければならないことからの脱却」を「休み」と定義したところで、休みにおいて真剣に何かに没頭するのであれば、それもまた「したいこと」に近い「しなければならないこと」ですよね。
それに、理想的には、したいことを仕事にすることが良いわけですし、そうすると仕事も休みない……。
仕事も休みもないっていうなら、それらすべては人間の営みであるので、その反対にあるのはその営みがない状態、つまり「死」ということになるでしょ。すると、本当の休みは死んでからはじめて訪れる、といえますね。不思議な話ですが。
──根本の概念と向き合うと、安易に二項対立でとらえないことの大切さがよくわかります。
「休み」と「仕事」といったように、物事を二分法で分けるのは、人間の思考の癖ですね。敵ー味方、善ー悪といったように。確かにこれはわかりやすいですが、わかるようにしかわかってない。
鎌倉時代の禅僧道元(1200-1253)は、「迷いは同時に悟りである」という言葉を残しました。
二分法では捉えられないものがある。白と黒が合わさった太極図は、二分法ではない世界を的確に表しているように思います。

学校の語源は「余暇」 休みと学びの関係
──先ほど「休み」の反対は「存在」、つまり休みとは死のことのような話もされましたが、もう少し具体なところで、「仕事」の対義語ではない「休み」について先生はどう捉えていますか。
「休みとは何か」を考えるヒントに、ラテン語の「スカラー」という言葉があります。
スクール(school、学校)、スカラー(scholar、学者)、スカラシップ(scholarship、学問)などを表す英語は、ラテン語のスコラ(schola、学校)に由来します。
そして、ラテン語のスコラは、ギリシア語のスコレー(余暇、ひま)からできた言葉といわれます。いわゆる「ひまな人」が、パトロンに養ってもらって学問をしたと言われています。
──学校や学者、学問の語源は、なんと「余暇、ひま」だったんですね。
少し調べたところ、ギリシア語のスコレーは、現代の私たちにとっての「余暇、ひま」という意味だけではないのです。スコレーには「積極的精神活動」という意味もあります。積極的精神活動とは、自分を見つめるもう一つの目の具現化とも言えます。
つまり休みとは、自分自身を振り返る、自分に迫るという面もあるのです。

──休みとは、自分について振り返ること。これには、どんな効能があるのでしょうか?
アメリカの哲学者ラルフ・ウォルドー・エマソン(1803-1882)は、こんな言葉を残しています。
人は、詩人や賢人の天空の光沢よりも、自分の心の内側から輝き出る一筋の光を発見し見守ることを学ばねばならない。それなのに人は、自分の思考が自分のものであるという理由で、これには目もくれずに忘れ去ってしまう。
「自分の心の内側から輝き出る一筋の光」は、自分の中にあるのです。自分の心の内側から湧き出る疑問は大事です。自分の声に耳を澄まして自分自身に迫るほうがいい。
たとえば古代ギリシャの哲学者はとことん他者と対話して、とことん自分を見つめ、とことん自分を疑った思想だから、2000年経った今も残る「普遍性」を感じることができたのだと思います。自分を考えることは自分に固執することじゃなく、むしろ自分を無くすってことなんですよね。
本当の「問い」と向き合うために、私たちに必要なこと
──休むという積極的精神活動によって、自分のなかにある思想や疑問を探り当てること。そこから学問が生まれていたんですね。
学問においては、問いの立て方がとても重要です。
「仮説を立てて検証していく」のは学問の営みとして知られていますが、どんな仮説を立てるのか? つまり問い一つでその研究の意義が変わります。
学問においては、その問いを持ち、とことん疑い、それでも精査したところに真理なり、価値ある知見なりに近づけるのだと思うのです。その問いの質が低いと、陳腐な研究に勤しむことになってしまいます。
──「問いの質が低い」とは、一体どのようなケースでしょうか。
ノーベル賞受賞者や、高いポジションにある方々から「自分の興味関心のあることを大事に研究しよう」という呼びかけを聞きます。含意のある言葉だなと思いますが、受け取る側の意識によっては「そうか、なんでもいいから、自分の興味関心を追いかければいいんだ」という捉え方にもなる。その結果、とても浅い問いを立てることにもなりかねない。

極端な例で説明しましょう。
ある研究者の興味関心があることが「東京=京都間の新幹線が2時間10分のところを1時間に縮める」だとしたら、どうでしょうか。
まず、時間短縮が本当に望ましいことなのか? を疑う必要がある。「往復時間を短縮して、これ以上忙しくなるのはやめてくれ」というビジネスマンの声を聞いたことがある人も多いでしょう(笑)。
そもそも、なぜその研究者がその問いを立てたのかも疑う必要があります。単純に、早いほうがいい、効率が高いほうがいいを是とするのは、ちょっと浅はかということです。
これは架空の事例に過ぎませんが、こういった目の前のわかりやすい不都合を都合に変える問いに邁進する研究者はよく見かけます。しかし、大事なのは、目に見えない方の「問い」だと思ってます。その問いがなぜ在るのかという問いです。
「対話」が生まれる場所を、どう作るのか。京大100人論文の工夫

浅い問いでも別にいいんです、本人がそうと自覚さえしていれば。自分の興味関心に対して自身で疑い、立てた問いに対して自身で問い直しとことん考える必要がある。学問をする研究者には、その営みがとても大事だと思いますし、その上での問いならどのような問いでもいのだと思います。
大事なのは、学問として、ちゃんと果てまで考えること、考えようとすること。そして、その「考え」を育てるのは、本質的な対話だと僕は考えています。
古代ギリシャの哲学者たちを例に挙げるまでもなく、本質に近づくには、疑いを重ねてとことん考え抜かせてくれる質の高い対話が欠かせません。そんな対話の場を生み出したくて私たちが始めたのが京大100人論文です。
──京大100人論文とは、どのような取り組みですか?
京大100人論文は、2021年で9回目を迎えました。さまざまな分野の研究者が自分の研究テーマに関する「1つの写真」と「3つの設問」を掲示し合い、オンライン上で匿名でコメントし合います。掲示数は146、貼られた付箋紙の数は3000枚を超える盛況のイベントとなりました。
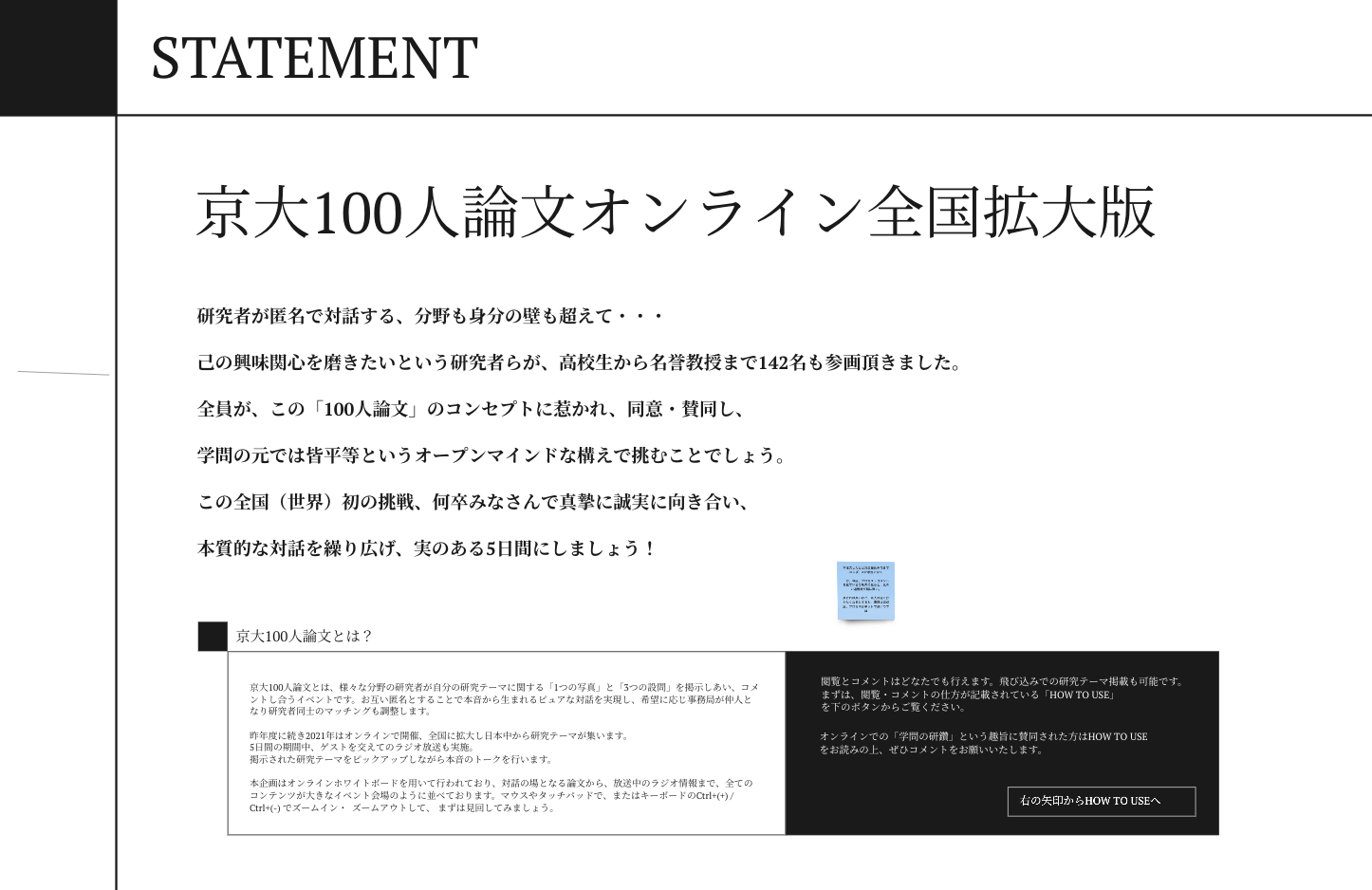
──今年は、どんなことが心に残っていますか。
ひとつ例を挙げるなら、言語学者やAIの研究者たちが集まって、数式の曖昧さについて話し合った公開対話「嗚呼、言葉の世界よ…」はおもしろかったですね。
数式に対して完璧なものというイメージを持っている人も多いでしょうが、実は関係性を示しているだけなので曖昧さがあるんです。楽譜でいえば、同じオーケストラで同じ楽譜を使っても、指揮者によって演奏が変わります。これは、指揮者による楽譜の解釈が入るから。数式も、「(そのメッセージが)解釈によって変わる」という点が楽譜と共通しています。
公開対話では、そこから「言葉ってなんだろう?」と話が広がっていきました。京大100人論文では、そういったいくつもの本質的な対話がなされました。

対話により研鑽を積む、新しい対話型学術誌『といとうとい』
──今年、新しい学術誌「といとうとい」を創刊されました。これはどのような取り組みでしょうか。
2021年6月に創刊した「といとうとい」の特徴は、対話型学術誌という点です。
「なぜそのテーマを研究するのか?」研究者の興味関心を高め合う目的に重点を置いています。Vol.0では、新しいフィールドを切り拓こうとする研究者による8つの論考と、著者と編集委員・識者の対話を掲載しました。

──創刊の背景には、どのような思いがあったのでしょうか。
対話型学術誌の創刊には、現状の学術界への問題意識がありました。
現状の論文にはフォーマットがあります。諸言、目的、実験方法といった、それぞれの分野ごとのおさえるべき仕来り、お作法のようなものがあって、それに則ったら「読める論文が書ける」保証にもなっています。
裏を返せば、フォーマットさえ押さえていれば誰かの査読を経て、掲載できるわけです。本来、その研究の価値そのものは、その瞬間の判断では問えないですよね。
例えば、ダーウィンの進化論だって当時は暴論という扱いでした。だから、フォーマットさえしっかりしていれば、その内容の判断は後世にゆだねるというか、そういう意味合いもあって、論文においてはフォームというものが重視されるようになっているわけです。
でも、すべてのものに置いて光と影があるように、悪い面もある。僕はその悪い面が気になっています。

──悪い面とは、ズバリ何でしょう。
形式主義です。内容じゃなくて、「きちんとフォーマット通りに書けているかどうか」、あるいは「どの雑誌に載ったか」が論文の良さを判定する指標になることが挙げられます。
形式主義によって、その形式を守ることに意義が生まれてしまっている。それをもみんなで疑うという営みをする必要があると思っています。
思いを磨き合う学術誌をつくるためにはどういったしつらえがいるだろうか? 『といとうとい』では、編集担当の矢代真也さんと対話し、考え抜きました。
例えば、『といとうとい』は、言葉や論理も疑った結果、写真家・伊丹豪さんの写真と合わせることで感覚を呼び起こすようなしつらえになっています。これまでにない学術誌を作ったと自負しています。

デーモンのささやきを聞く。自分の心の声に正直に生きる
──草刈りや学問、京大100人論文や新学術誌の創刊に至るまで、宮野先生の溢れるパワーに圧倒されます。どうしてそこまでいろんなことに情熱を傾けられるのでしょう?
だって気になるんです。どうして気になるのかはわからない。けれども、気になる。だからのめり込みたくなる。そんな自分の感覚に、敏感で誠実にいようと思っています。
これまで、机のDIYや車のカーステレオづくり、マウンテンバイク、家庭菜園。そして9年目を迎えた京大100人論文や、『といとうとい』の創刊に、全力を投じてきました(笑)。
成果や結論を想定して、理知的に判断しているわけではないのです。むしろ「その道を進むと困難が多い」「進まないほうが楽だ」ということは頭ではわかっています。事実、京大100人論文などの企画終了後は、毎回死力を尽くすわけで、「こんなしんどいこと、もう二度とやらない!」って思うんですけどね。でも、またやってしまう。
これは、僕の中のデーモン(悪魔)が「もっとやれ」とささやくのに従っている、としか言いようがありません。
僕は、学者が一番忘れてはいけない、自分の不思議、驚き、好奇心を大事にしたい。これからも、自分の心の声に正直に生きていきたい。「世界が在ることに驚いて、生きる」とでも言いましょうか。僕は、自分が信じる学問というものを具現化をしていきたいのです。

…………
「休みと仕事、オフとオン。二項対立でとらえる必要はないのでは?」
宮野先生からストレートな問いを投げかけてもらった。ポジティブな逃避の時間を探究する「DIG THE TEA」も、現代人の生活に囚われていたのかもしれない。
仕事や情報に追われる忙しい日々は、自分自身との向き合う時間が足りないから。一人ひとりが自らの問いと向き合い、学び進んでいくことで、休みと仕事はどちらも人間としての営みになっていく。
「『DIG THE TEA』は、『時間とは何か』を哲学する挑戦だ」という言葉は、私たちの糧になるだろう。これからも、探究の旅は続く。
写真:木村有希
